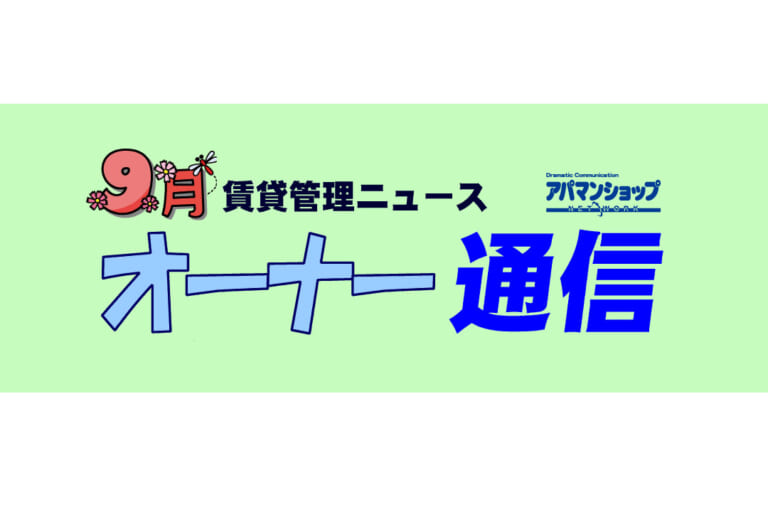- 2024.05.09


旧耐震基準の賃貸物件の貸主に耐震工事を行う義務はあるのか?
1981年5月まで適用された建築確認基準を「旧耐震基準」と呼びます。これは中規模の地震(震度5強程度)では倒壊しないレベルであり、大規模の地震(震度6強~7程度)に対する安全性については不安があるとされています。この旧耐震基準の建物の賃借人から「賃貸人の修繕義務として耐震工事を行うべき」と主張されことが問題となった裁判例(東京地方裁判所平成22年7月30日判決)を紹介します。
その物件は昭和43年築の6階建ビルで、平成10年に月額賃料約300万円で賃貸借契約が締結され10年ほど経過していましたが、平成18年の姉歯事件で建物に不安を覚えた賃借人が第三者機関に耐震調査を依頼しました。その結果がC1ランク(補強が必要である又は精密診断を勧める)であったため、賃貸人に補強工事を求めたものの、これを拒絶されたため紛争になったという事案です。
築年数が古いビルですが、外壁や内装は度々工事しており、他の賃借人からのクレームも特になかったという経緯があります。裁判で「賃貸人に旧耐震基準の建物の耐震改修義務があるか」という点について争われることとなりました。賃借人は以下の理由をあげて賃貸人の耐震改修義務を主張しました。
- 本件建物は多数が利用する事務所を前提としている。本件報告書に示された耐震性能では、賃貸借の目的に沿って安全かつ安心して使用することは不可能である。
- 本件建物は高額賃料の営業物件である。
- 昭和43年築の本件建物は昭和46年(1971年)の建築基準法改正の耐震基準すら満たしてない。
この賃借人側の主張に対し裁判所が下した結論は、「賃貸人に耐震改修の義務はない」というものでした。その理由として、賃貸人に課せられている修繕義務について裁判所は、
修繕義務の内容は、契約の時点において契約内容に取り込まれた目的物の性状(性質と状態のこと)を基準として判断されるべきであり、仮に目的物に不完全な箇所があったとしても、それが当初から予定されたものである場合は、それを完全なものにする修繕義務を賃貸人は負わないというべきで、賃貸借契約の締結当時の建物、もしくは契約で合意された性状を基準として修繕義務は判断すべきである。
と述べました。左下の基準を前提として、本件建物が昭和43年築の建物であったとしても、
- 本件建物はその建築当時の建築基準法令に従って建築されているものというべきであり、かつ現時点において要求される建築基準法上の耐震性能を有している必要はなく(※既存不適格建築物)、さらに本件建物の建築年次は登記情報等により誰でも確認可能であって、当該建物がどのような耐震基準を満たしているのかは借主側でも確認可能であったこと。※すでにある建築物で現在の建築基準法には適合していないもの
- 本件契約締結時に本件建物の耐震性能が特に問題とされた事情はうかがえないことからすれば、本件契約では本件建物の耐震性能につきその建築当時に予定されていた耐震性能を有していることが内容となっていること。
- 契約継続中に本件建物の利用に当たって具体的な問題が生じているわけではない。
と延べ、賃貸人に修繕義務は存在しないと結論づけました。裁判所の考え方をまとめると、
- 賃貸借契約を締結する時に、耐震性能が問題となったかどうか、または、賃貸物件が最新の耐震性能を満たしていることが契約の内容となっていたかどうかが問題となる。最新の耐震性能を満たすことが契約内容となっていた場合は、それを満たすよう賃貸人は修繕をする必要があるが、耐震性能を特に問題としなかった場合は、その建物が建築当時に予定されていた耐震性能を有していれば良い。
- ただし契約継続中に賃貸物件の利用にあたって具体的な問題が生じた場合は、賃貸人においても対応が必要になる場合がある。
と言えるでしょう。
このように、賃貸人の耐震工事を行う義務は原則として否定されていますが、一方で、賃貸人には「民法717条の土地工作物責任」があります。
万一、強大な地震などで賃貸建物の崩落等が発生し、賃借人に損害が生じた場合には、この適用により物件の所有者たる賃貸人にも責任追及が及ぶリスクはありますので、賃貸人としては、このリスクを認識したうえで、賃貸物件の耐震性能を意識して経営する必要があると考えられます。
公示地価2024・3年連続の上昇でバブル期以来に
マンション高騰で地価上昇傾向が続く
2024年度の公示地価が3月26日に公表されましたが、今年も全国的に住宅地や商業地の上昇傾向が続いています。特に都市部や交通至便エリア周辺の上昇が顕著になっており、三大都市圏などではマンションの高騰によって、価格が手頃な周辺部へ需要が拡がっているようです。
一例として、千葉県市川市や流山市など、都心へのアクセスが良い住宅地が10%を超える上昇率を記録したように、都心はマンション価格が高くなりすぎて、子育て世帯の中には郊外に新居を求める人が増加中で、平成のバブル期を彷彿とさせます。
地方都市でも、再開発や交通インフラの整備が進むエリアで地価上昇が見られていて、東名阪に次ぐ札幌、仙台、広島、福岡の地方中枢都市では全体で7%の上昇率を示しています。
半導体バブル。熊本、北海道の次は宮城
半導体工場の進出による雇用創出と住宅需要の増加で20%前後も地価を押し上げているのが北海道千歳市や熊本県菊陽町です。最近では、地価上昇の代表としてテレビ・新聞で紹介されていますが、工場の本格稼働は、熊本で2024年末、北海道では2027年4月頃の予定といいますから、周辺への影響はこれからも続くとも予想されていて、半導体威力の凄まじさを感じます。
昨年、仙台市近郊で半導体工場が新設されると報道された宮城県内の公示地価は、仙台市周辺9市町村で上昇が続き、特に、仙台市近郊の富谷市や大和町ではこれから本格的な地価高騰が期待されています。その一方、沿岸部の23市町では下落傾向が続いていて二極化が顕著になっています。
ちなみに、半導体工場の建設地はまとまった平地があることに加え、豊富な水資源の確保が必須で、さらに輸送に便利な空港に近い土地が求められるそうです。確かに、熊本、北海道、宮城は全てこの条件に合致しています。同条件を満たすエリアは、いつか半導体バブルの恩恵にあずかれるかもしれません。
北海道・長野ではスノーリゾート開発
昨年から続くインバウンド需要の回復も地価に好影響を与えています。北海道富良野市では、外国人向け別荘やコンドミニアムの需要増加により、住宅地の上昇率が27.1%で住宅地として全国トップとなりました。
北海道札幌市内の不動産投資家は、「北海道ニセコの開発を牽引した香港系の不動産ファンドが大量に土地を取得している。ニセコで稼いだ2匹目のドジョウを探す動きが活発になってきており、富良野が上昇気流に乗ったのは間違いなさそう」と地元の事情を語ります。
長野県では白馬村が県内最高の19.5%(住宅地)、野沢温泉村が15.0%(住宅地)を記録しました。どちらも国内でも有数のスキー場があり、スノーリゾートへの開発マネー流入が背景にあります。
リゾート開発に詳しいビジネス誌の記者は、「日本には80年代のスキーブームの頃から設備投資されていないスキー場が多数ある。雪質の良さに加えて、設備投資することで価値を引き上げられる点に気付いた海外の投資家が国内のあちこちに目を付けている。富良野や野沢温泉に加え、岩手県の安比高原も次の開発候補に上がっている」と語っています。
北陸新幹線延伸の福井、影響は限定的か
鉄道の新路線整備も地域の地価を押し上げる要因となっています。福井県内の商業地の平均変動率は0.2%増となり、実に32年ぶりの上昇を記録しました。北陸新幹線金沢―敦賀間の開業で、福井市を中心に地価が上がり、全体を押し上げたことが好影響を与えました。
地元の不動産会社は、「新幹線効果で福井駅や敦賀駅周辺でホテル建設や商業施設などの需要が増している。ただ影響はまだ駅周辺だけで、住宅地も併せた県全体の地価は0.1%のマイナスなので、新幹線効果がどのくらい続くかはわからない」と影響を見計らっている状況です。
今後の地価の見通しについて経済メディアの記者は、「マイナス金利は解除されたが日本銀行の緩和傾向は続いており、住宅ローン金利の大幅な上昇は考えにくく、地価は緩やかな上昇傾向を維持すると予想する声が多い。
ただ、都市部と地方の格差は拡大傾向にあり、不動産オーナーは、立地条件や周辺環境を十分に見極めた上で、安易に上昇を期待するのではなく、慎重に投資判断を行う必要がある」と語っています。
大家さんのための税金基礎講座
2024年贈与税改正。暦年贈与と精算課税、どっちが有利?
Q.今年(2024年)から贈与税が改正になりましたね。昨年から学んでいるのですが、もう一度シンプルに、2023年までとの違いや、どちらが節税に有利かなど、解説してください。
A.2024年の贈与税改正は、「一部は増税で、一部は減税」と評することができます。増税とは、暦年贈与の「3年内加算が7年に延長された」ことです。年数が伸びたことで節税が難しくなりました(孫などへの贈与は今まで通り)。減税とは、相続時精算課税に「年110万円までの非課税枠が創設された」ことです。これを利用することで節税できるようになりました。詳しく解説していきましょう。
ご存じのとおり、贈与税には、暦年贈与という原則と、相続時精算課税制度(以下、精算課税)という例外的な、2通りの課税方法があります。暦年贈与には年110万円の非課税枠があり、これを活用すれば、一人の子や孫に対して10年間で1,100万円を税負担なしで贈与できます。
18歳以上の子や孫に年500万円を贈与した場合でも、年485,000円(控除10万円税率15%)の贈与税を負担することで、10年間で5,000万円を贈与することができます。暦年贈与が生前贈与の王道と言われた所以(ゆえん)です。
しかし暦年贈与には、亡くなる直前の駆け込み贈与を防ぐために、「亡くなる前3年間の贈与はなかったことにする」という規定がありました。これが2024年から7年に延長されました。前述の10年で5,000万円贈与の例では、改正前は3年分1,500万円の贈与がなかったこととなりますが、改正以降は7年分3,500万円に増えてしまうので、これが増税となるわけです(この改正は2024年1月1日より適用されるので、実際に7年分まで加算されるのは2031年以降)。
ただし、3年より延長された期間(上の例では4年間)は100万円まで非課税という例外規定も設けられました。ともかく、10年間の暦年贈与で、節税効果が得られたのは最初の3年だけ、という結果になり得るのが今回の改正、というわけです。
一方の相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母が、18歳以上の相続人および孫に、通算2,500万円まで贈与しても非課税、という制度です。贈与時に税金は課税されませんが、贈与者が亡くなったとき、過去に贈与した財産はすべて遺産にプラスして相続税が計算されるので、節税にはならないことから、あまり利用されていませんでした。
しかし2024年から精算課税に「年110万円までの非課税枠」が創設されました。この110万円は、相続時に遺産にプラスされることなく、年数の制限もなく、もちろん7年以内加算などもありません。初年から贈与者が亡くなるまで、非課税で110万円を贈与し続けることができます。
これによって、精算課税でも節税効果を得ることができるようになりました。ただし、精算課税を申告した後は、暦年贈与に戻ることはできません。また、暦年贈与と精算課税は相続人ごとに使い分けることができます。以上が2024年贈与税改正のあらましです。
まとめてみましょう。2023 年までは、暦年贈与を使って生前贈与するのが王道でした。精算課税には節税効果はないのですから、節税が目的なら暦年贈与を利用すればOKという、シンプルな考え方でよかったのです。
しかし今回の改正で、節税に有利だった暦年贈与に、加算が7 年に延長という増税策が講じられ、節税効果のなかった精算課税に110 万円の非課税枠が創設されたことで、「どっちを選択したらよいか」の答え探しが複雑になりました。いったい、どちらの方が節税効果が高いのでしょうか?
この問いに、ひとつの正解はありません。財産総額、贈与期間、贈与金額の選択などによって節税効果が違ってくるのです。一般論では、贈与年数が短く、財産総額が少ない場合は、精算課税が有利で、反対に贈与年数が長く、財産総額が多い場合は、暦年贈与が有利となります。
つまり、贈与年数が短いと、暦年贈与では7 年以内は相続財産に加算されますが、精算課税では110 万円以内の贈与は加算されないため、精算課税が有利になります。
一方で、贈与年数が長い場合は、暦年贈与では適度な金額(たとえば年に500 万円)を贈与して多少の贈与税(18 歳以上の子や孫なら48万5 千円)を払うことで相続財産を減らすことができますが、精算課税は110 万円を超える贈与は、すべて相続財産に加算されてしまうため、暦年贈与のほうが有利になるのです。
毎年コツコツ110万円以内を贈与して確実に節税できるのが精算課税。贈与者の7年以上の健在を前提に、110万円を超える贈与によって高い節税効果を得るのが暦年贈与。このようにまとめることができます。

- Tags
- 人気のタグ
- Rerated
- 関連記事