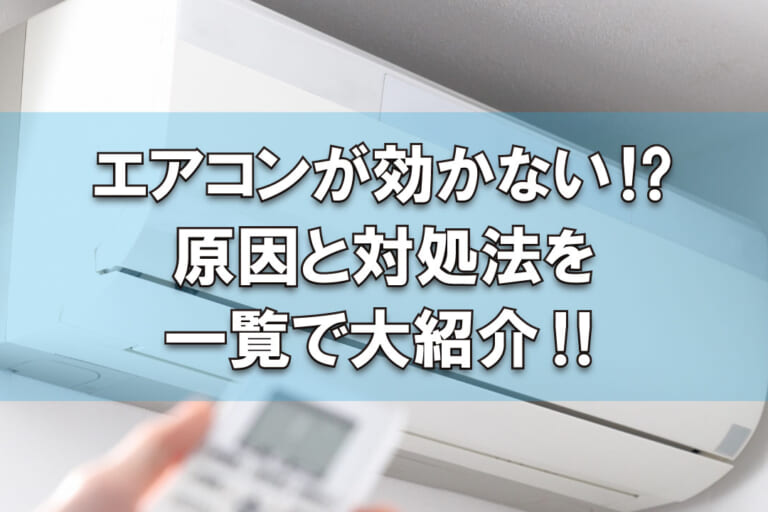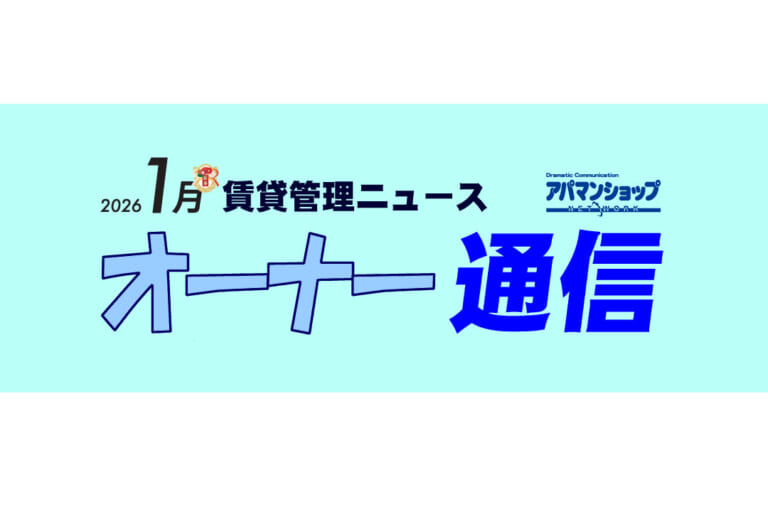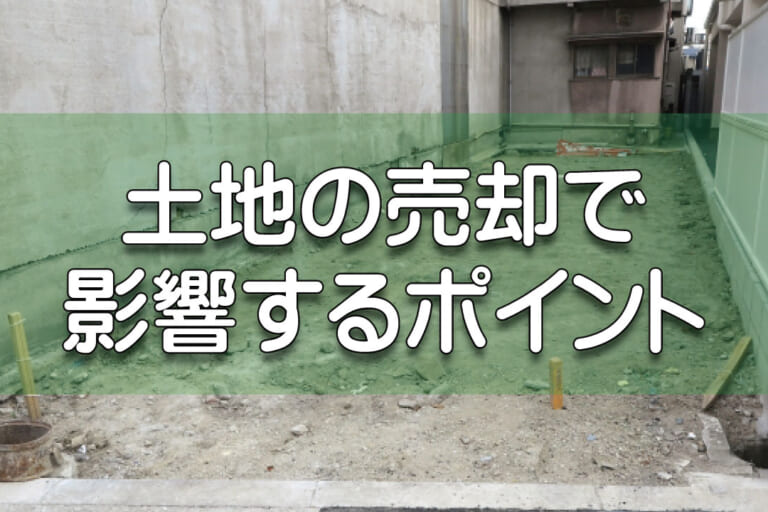- 2024.12.07
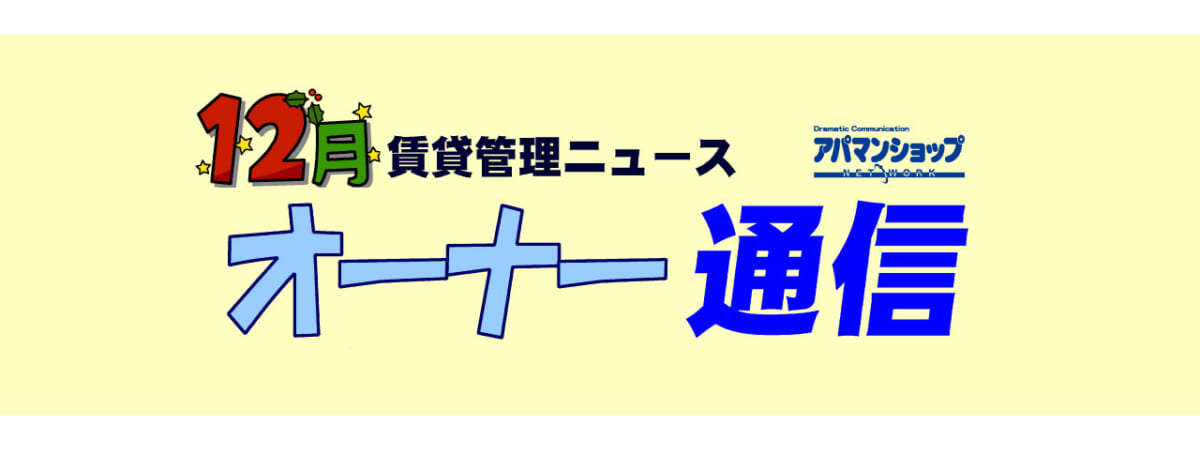

貸主の修繕義務と借主の立ち入り拒否権の関係
賃貸借契約において賃貸人は、賃借人が使用する建物の修繕をすべき義務を負うとされていて、民法606条で以下のように定められています。
【民法606条】
- 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
- 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
具体的にどの範囲まで賃貸人が修繕義務を負うのかということは、個々の賃貸借契約で定められていますが、一般的な住居の賃貸借契約では、電球等の消耗品以外の修繕については、概ね賃貸人が修繕義務を負うことが多いでしょう。
そうすると、賃貸人がこの修繕義務を果たすためには、賃借人の使用部分(居室など)への立ち入りが必要となる場合も多々ありうることとなります。
このため、民法606条2項において、賃借人は、賃貸人が保存行為を行う場合にはこれを拒否できないと定めています。
なお、606条2項は「保存に必要な行為」としていますが、これは「賃貸目的物を保存し維持するために必要な修繕行為」を当然に含むものと考えられます。
このように、建物の賃借人は,賃貸人が行おうとする賃貸建物の維持修繕等の保存行為に対して受忍する義務を負っています。
したがって、建物の維持修繕等の保存のための調査や工事を、当該賃借人の賃借部分(居室部分等)で実施する必要があるときは、賃借人は正当な理由なくして自己の賃借部分への立入り等を拒むことができないということになります。
以上を踏まえると、賃貸人が協力を要請する調査や工事が、建物の維持修繕などの保存に必要と認められるにもかかわらず、賃借人がこれを正当な理由なく拒むときは、賃貸借契約上の債務不履行を構成すると解釈されます。
修繕等は、通常は賃借人にとっても利益になることですので、立ち入りを拒むことはあまり起こりえないことではありますが、過去の経緯から賃貸人と賃借人との間で感情的な対立が生じていたり、修繕に至るまでのプロセスで意思疎通がうまくできなかった場合などでは、賃借人側において調査や工事のための立ち入りに難色を示すということもあります。
では、賃貸人が建物の保存に必要な工事等の調査目的で賃借人の居室に立ち入りを求めたものの、賃借人が正当な理由も無く拒絶をした場合に、賃貸人は債務不履行であると主張して賃借人との契約を解除することができるのでしょうか。この点が問題となったのは、東京地方裁判所平成26年10月20日の事例です。
本事案は、ある賃借人の居室の天井から水漏れが生じたため、原因究明のために、賃貸人がその上階の賃借人の居室への立ち入りを求めたものの、上階の賃借人があれこれ理由を付けて拒絶したため、賃貸人が契約の解除を主張して提訴したという事案です。
この事案において、裁判所は、まず、賃借人が立ち入りを拒絶した理由についてはいずれも合理的根拠がないとし、
「漏水に関して本件居室の立入調査が実施できていないのは、賃借人が正当な理由なくこれを拒絶しているためであり、このことは、本件賃貸借契約上の債務不履行を構成する。」
と認定した上で、それを解除事由とできるかは、
「賃貸借契約の基礎をなす賃貸人・賃借人間の信頼関係が破壊されたと認められるかどうかの検討が必要」
とし、“信頼関係が破壊されたか否か”については、
「賃貸人が賃借人に対して漏水の調査のための立ち入りを求めるにあたり、賃貸人としてなすべき努力を十分に尽くしていたにも拘わらず、賃借人側が、一度も調査に応じる意思を明示せず、また、立ち入りを認めるための条件として、漏水とは全く関係のない、居室の設備等の修繕等を求め、その完全実施を漏水調査への協力の条件とするかのような内容の回答をしたことをもって、この段階において信頼関係は破綻されるに至ったというべきである」
として、契約の解除を認めました。
この事案では、過去にこの漏水以外でも、賃借人側が賃貸人側に対し過度に神経質とも取れるような対応をして紛争を生じさせていたことがあり、その事情が認定されたことが信頼関係破壊による解除を認めた一つの要因と考えられます。
この点で本件は若干特殊な事例と言えなくもないのですが、いずれにしても、賃借人が不当に建物の維持・保存に必要な修繕の調査や工事を拒む対応を続けた場合には、契約の解除原因になり得るということを示した一つの事例として参考になります。
中国・韓国・米国の不動産不況-賃貸経営に与える影響は?-
中国、韓国、米国の最新の不動産事情をみながら、日本の賃貸住宅経営への影響を考えます。
「中国不動産バブル崩壊」、影響は限定?
中国の大手不動産企業、碧桂園(カントリー・ガーデン)が資金調達に苦しみ、事実上の破綻状態とも言われています。中国全体の経済が厳しい中、特に不動産市場は新築住宅の販売も思わしくなく回復の兆しは見えません。
中国メディアでは、日本のバブル崩壊を引き合いに出して、長期の不景気に陥る可能性が示唆されていて、日本でも「中国不動産バブル崩壊か?」の報道を目にします。日中の経済的な繋がりを考えれば、日本への影響も懸念される事態と言えそうです。
しかし、今のところ中国政府は未完成物件の引き渡しを優先し、デベロッパーが倒産しないようサポートしていて、不動産市場が急激に崩れる可能性は低いと考えられているようです。
さらに、中国の銀行の不動産業者への貸し出しは、全体に占める割合がそれほど高くないため、金融システムへの大きな影響は限られているようです。日本が90年代に経験したような、金融機関による貸し渋りや貸し剥がしによるダメージは、今のところ予想されていません。この辺りは「日本に学んでいる」と言えるのかもしれません。
韓国マンション市場も急ブレーキ
中国ほどは報じられませんが韓国の不動産市場も急速に冷え込んでいます。日本の日銀にあたる韓国銀行が、2020年に0.5%だった政策金利を、2023年までに3.5%まで引き上げたことで、住宅ローンの金利負担が急増し不動産投資に急ブレーキがかかり、マンション価格の下落を招く結果となりました。
また、韓国独自の仕組みであ「チョンセ」を活用したギャップ投資(住宅価格とチョンセ価格(保証金)の差額だけで物件を購入するもの)も立ちゆかなくなってきました。政府は税制緩和などの対策を打ち出していますが、今後も不動産価格の下落が続くと予測する声が多く市場は不透明です。
ただ韓国と日本との経済的な結びつきは、半導体や観光などの一部に限られているので、中国や米国の不動産不況と比べて、我が国に与える影響は少ないと思われます。
深刻なアメリカ不動産市場の劇的な変化
より深刻なのは、アメリカの商業用不動産市場ではないかという声もあります。海外の調査機関によると、2022年4月から2023年8月の1年4カ月で、アメリカの商業用不動産の価格は16.5%も下落したそうです。これほどの下落はリーマンショック以来ですが、まだ下げ止まりにはほど遠く、今後も下落が続く可能性が予想されています。
特に顕著なのはオフィス物件で31%も価格が下落していますが、これには、コロナ禍で普及したリモートワークが影響しているとされています。全米の労働者の10%以上が、1週間で1度もオフィスに出社しない完全リモートワーカーとして働いているとされ、さらに3人に1人が自宅勤務とオフィス出社を併用しているそうです。
日本より早くコロナの影響から脱したアメリカですが、企業はオフィス面積を減らし続けています。コロナの影響を超えて「オフィスで働く」という考え方に大きな変化が起きているとみられています。ちなみに、自宅で買い物するネット通販の需要が増加していることもあり、倉庫物件の価格は8%の下落にとどまっています。
商業用不動産の下落の影響は不動産市場に留まらず金融機関にも及んでいます。特に地方銀行(中堅・中小銀行)では不動産向けの融資割合が20%以上もあるので、もしも不動産が不良債権化すれば銀行自体の経営への影響は避けられないでしょう。
さて、この海外の不動産市場は日本にどう影響するでしょうか? まず、安全な投資先を求めて日本の不動産市場にマネーが流れ込む可能性があります。さらに執筆時点で1ドル=150円台まで円安が進んでおり、世界的には日本の不動産は割安と見られている点も見逃せません。都心のマンション価格はバブル期を超える高騰を見せていますが、アメリカや中国の不動産市場に留まっていたマネーが日本市場に向かえば不動産価格はさらに上昇するでしょう。
一方でアメリカの不動産不況が金融市場に深刻なダメージを与えるようであれば世界的な不況になる可能性もあります。仮にリーマンショックの再来になれば日本の景気悪化も避けられず、法人契約の解除や家賃滞納が増加するなどの影響もあるでしょう。
また金融機関が融資を厳格化することで不動産価格が急落する可能性があります。物件の売却が困難になる一方で、物件を買える原資が用意できる投資家にとっては安く物件を手にするチャンスになります。遠い海外の不動産事情ですが、日本の経済や不動産、さらに賃貸経営に与える影響はゼロではありません。今後も注意深く見ていく必要がありそうです。
高齢者一人暮らしのリスクを回避する方法は?
先日、同業の賃貸管理スタッフの集まりがあり、参加者の一人から以下のような報告がありました。
築25年の木造アパート(和室6、洋間6、DK6)に新築から入居されたご夫婦がいる。ご主人58歳、奥様56歳、二人とも元気で収入もしっかりしていた。しかし、入居後14年目に奥様が亡くなり一人世帯となる。そして2023年の秋に、ご主人が寝具の中で亡くなっているのが発見された。
死因は病死で83歳だった。発見が亡くなって7日後だったので、大家さんと相談の上、つぎの募集では家賃を1割下げて「告知事項あり」とすることになった。大家さんは事故物件となることを懸念して「高齢者の一人暮らしの方には貸さない」という方針だったが、今回の事情では防ぐことはできなかった。「管理会社はどう対応したらいいのでしょうか」
今回は「高齢者の入居問題」について考えます。
2年ほど前のNHK「クローズアップ現代」では、事故物件や孤独死を何回か取り上げていました。当時は新型コロナによって、その数が増加傾向にあったからでしょう。番組で紹介された大家さんが、所有アパートの一部屋が事故物件となったときの顛末を説明したあと、「2度と経験したくないので高齢者には貸しません!」と話していたのが印象的です。この番組でいくつかのキーワードが示されましたので検証してみます。
「4人に1人が65歳以上」
日本は高齢化に突き進んでいます。令和3年10月のデータでは、総人口の28.9%が65歳以上となり、すでに4人に1人を超えています(内閣府)。65歳以上が3人に1人となる日も遠くありません(2036年という予想あり)。60歳以上の持ち家比率79.8%(2018年の住宅・土地統計調査)ですから、2割の方は賃貸で暮らしていることになります。お部屋を供給する貸主側からみると、“借り手”というマーケットが増え続けることになります。空室の長期化による収益の悪化に悩む大家さんにとって、無視できない市場であることは確かです。
「事故物件に住みたくない人は7割以上」
一方で、ひとたび事故物件となると借り手が極端に少なくなるのも現実です。事故物件とは、「殺人や自殺などで人が亡くなった部屋」を指しますが、その中に「病死や自然死で発見が遅れたケース」も入るとされています。高齢者の一人暮らしは「その可能性が高い」と考えられて敬遠されるのですね。では実際はどうでしょうか?
実は、孤独死の全国的な統計データはありません。そこで、一般社団法人日本少額短期保険協会の孤独死対策委員会が2022年に発表したデータを参考にしてみます。ちなみに、この委員会は、孤独死に関する認知・啓蒙活動を行っている団体だそうです。
その調査によると、孤独死で亡くなった方の平均年齢61.9歳、死因の66.8%が病死、60歳以上の割合60.8%、70歳以上の割合29.9%となっています。60歳以下の割合が4割で60歳以上が6割ですから、やはり高齢者に多い、という認識に間違いはないようです(個人的には想像したより顕著でないと思いましたが)。
ここで課題となるのは、「いかに事故物件としないか」という仕組みやルール作りですね。万一に対応してくれる近隣在住の近親者の身元引受けを条件とする、地域の福祉活動関係者や地域住民と協力して「見守る態勢」をつくる、セコムやAI機器の活用で異常事態をリアルタイムで把握する、新聞や高齢者向け弁当などの毎日宅配システムによって訪問回数を増やす、などの方法が、前述の管理スタッフの集まりでも報告されていました。工夫する余地がない、というわけではありません。
「高齢者4人に1人が入居拒否を受けた経験」「大家さんの約8割が高齢者に拒否感を持つ」
高齢者の一人暮らしが敬遠される理由は「孤独死の不安」だけではありません。年金のみの収入で貯金も減る一方なら家賃の支払いにも不安があります。認知機能の低下によって生活に支障をきたす、という問題もあります。これらの複合的な不安から、高齢者の入居に拒否感をお持ちの大家さんが多いのです。
一方で、家賃支払いの心配なら、高齢者に対応している保証会社を利用することで取り除くことはできます。近親者とのダブル保証でもよいと思います。認知機能については、いざという事態には近親者の身元引受人に頼ることになるでしょう。こちらも策がまったくないわけではありません。
空いてもすぐに決まる物件なら、高齢者に目を向けなくてもいいと思います。しかし、絶対的な供給量が需要を上回っているのが現実で、築古や立地条件が不利な物件は対策が必要ですが、家賃の値下げや使える経費も限られています。
増加する高齢者マーケットは、ひとつの選択肢に間違いはありません。ただし、リスクを理解したうえで回避策をしっかりと検討する必要があります。

- Tags
- 人気のタグ
- Rerated
- 関連記事