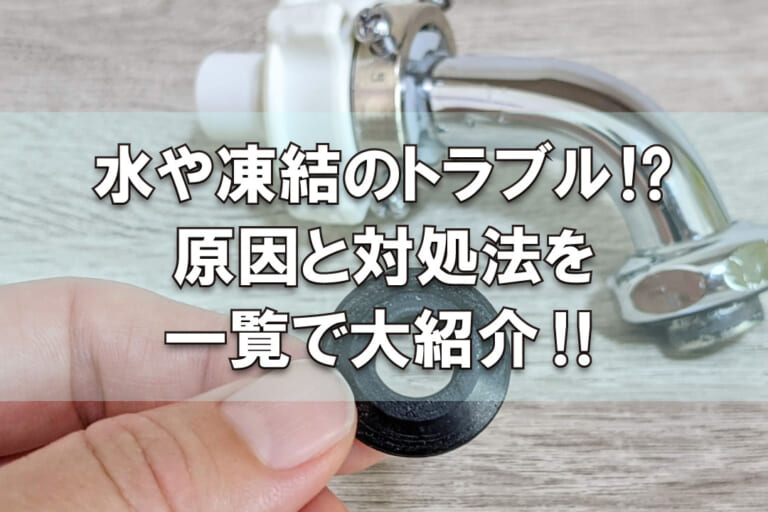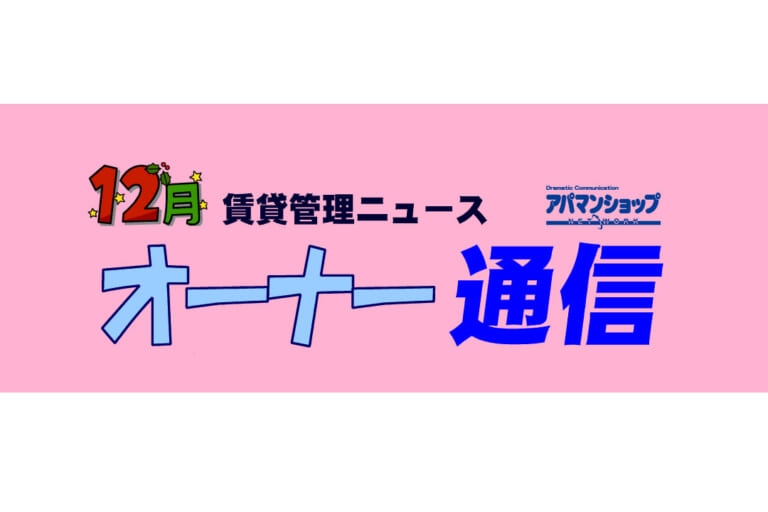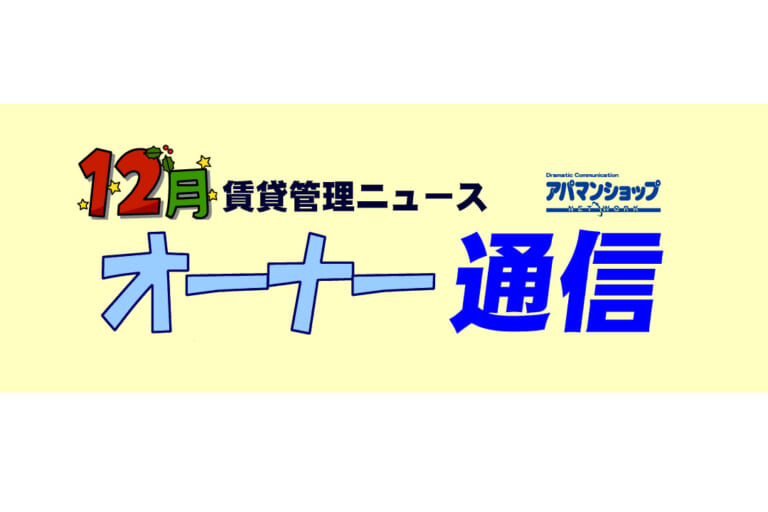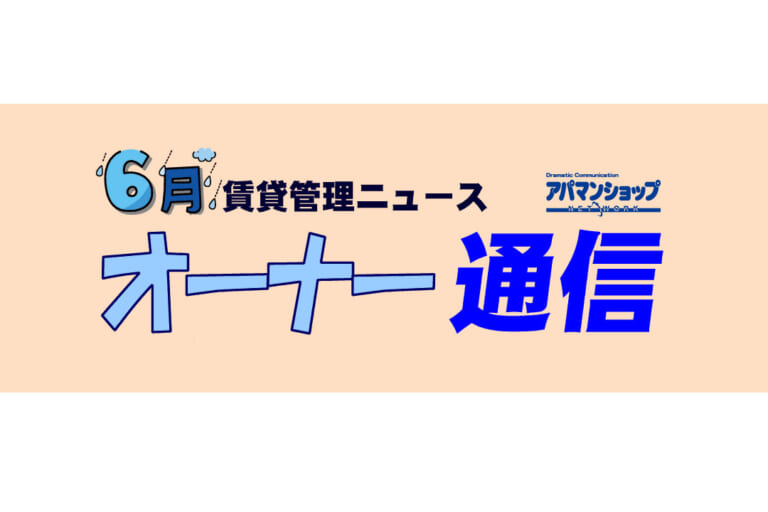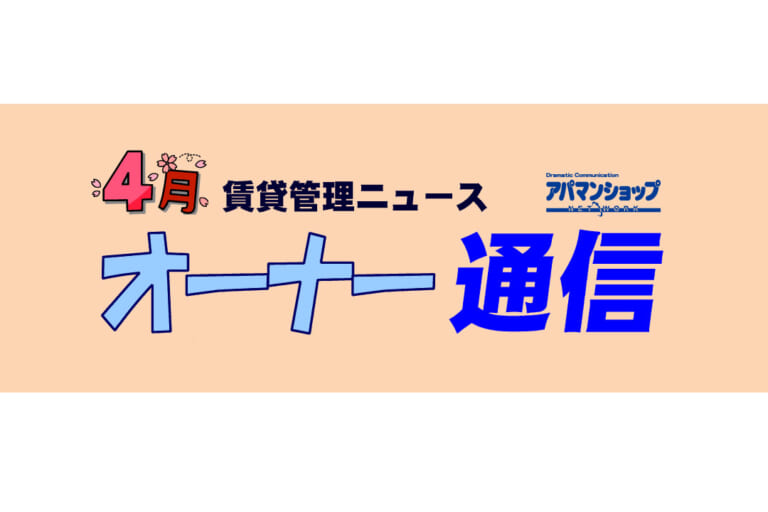- 2025.04.06
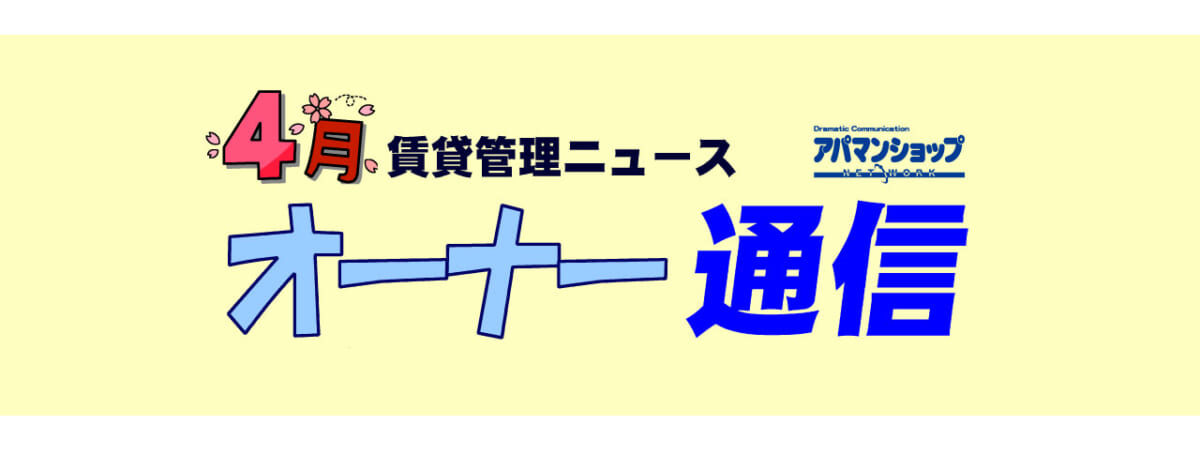
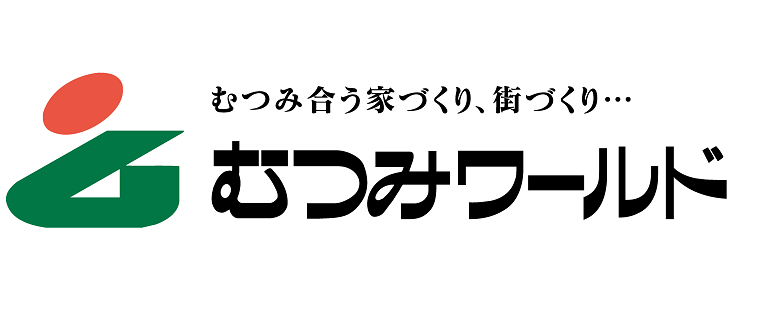
繁忙期明けの戦略を明確にしましょう
繁忙期に向けて空室対策に万全を期したのに、3月末で空室が残ってしまった賃貸物件。地域によって需要数と供給量のバランスがあるので必ずしも満室が叶うわけではありません。大切なのは「ここからどうする」という方針が決まっているか、ということです。
空室対策の基本に繁忙期と繁忙期後の区別があるわけでありません。ただ、お客様のニーズの変化に対応する必要はあります。まず、空室対策の基本6項目をおさらいしておきましょう。
1.借主のターゲートを想定する:想定することで設備やクロスの選別ができますし、初期費用と月額賃料負担額の上限を設定することができます。
2.リフォームや設備の改善を検討する:1で想定した賃料収入から逆算して予算が決まるので、その範囲でお部屋の改善を検討します。
3.募集条件を決める:募集条件には、賃料・礼金・敷金だけでなく、フリーレントや初期費用ゼロなどのサービスも含まれます。
4.賃料と物件価値のバランスをチェックする:2、3のバランスが合っていないとWEBで選択されません。
5.募集プロモーション(宣伝活動)を行う:目的はお客様にお部屋を内見してもらうよう誘(いざな)うことです。反響対応サービスの質も含まれます。
6.空室の維持管理:内見したお客様に気に入ってもらうように常に準備しておきます。
以上の基本が実施できていたかどうか?その簡単な確認方法をお伝えしましょう。
「空室となったお部屋に何組が内見に訪れたか」。その数を確認してください。もし極端に少ないのなら、上で述べた2から5の「どこか」が適切でなかったと考えられます。お客様に「現地を見てみよう」と想ってもらえなかった理由があるはずです。
たとえば、お客様はWEB上で必須設備と希望設備を選択して物件を限定していきます。必須設備とは、ターゲットが単身ならインターネット無料、女性ならオートロック、ファミリーなら追い焚き機能などです。
希望設備は、宅配ボックス、高速インターネット、システムキッチンなどです。ここで選んでもらえるように、
- 借主のターゲットを想定する
- リフォームや設備の改善を検討する
が適切に行われたか?を検討してください。
以上について自信があるなら、つぎは、その物件に対して賃料設定が適切だったか?その情報がWEBに効果的に発信されていたか?が検討課題となります。
簡単な確認方法の2つめです。
内見組数はそこそこはあったのに決まらなかったとしたら、6.「空室の維持管理」が適切でなかった可能性があります。お客様は物件を絞り込んできますから、現地まで足を運んでも決めなかった原因がお部屋にあったかもしれません。常にきれいで、ほこりもなく、変な臭いがしないことは大前提です。
スリッパ、マット、カーテンなどが設置されているとプラスですし、オーナーメッセージや入居者プレゼントなどのアイデアも迷っているお客様の背中を押してくれます。
以上のように、ここまでの募集活動の課題を見つけることが、この後の方針決定に役立ちますので、ぜひチェックしてみてください。
繁忙期後のこれからの方針を決めるには
CHECK1:ターゲット想定を再検討する
繁忙期は多くのお客様が期間限定で訪れますので、ターゲットを広めにしていたと思われます。一方で、繁忙期後は「気に入った部屋をじっくり探す」お客様が訪れるので、万人向けよりも個性に合った部屋の方が目に留まりやすいのです。そこで、さらにターゲットを絞った賃貸条件とプロモーションを検討してはいかがでしょう。
CHECK2:リフォーム及びリノベーションの検討
繁忙期は短期決戦ですが、これからは少し腰を落ち着けて、課題としていたリノベーション及び大型リフォームを検討してみるのも方針の1つです。築年数が15年か20年で、さらに今後も同じ年月以上の経営を続けるのなら、大物設備の入れ替えや間取り変更を検討するタイミングです。よいきっかけとなるかもしれません。
CHECK3:期間限定の特典
上とは真逆ですが「5月末までに決める」という目標を立てるなら、「5月中の契約者様に限り‥‥」として特典を用意するという対策です。特典は、フリーレント期間の追加や初期費用ゼロ、希望する設備の設置などです。この告知はWEB上では目を引くと思います。
満室経営に必要なのは、
- 空いたお部屋を早く決めること。
- 退去を防いで空室を発生させないこと。
この2つは同程度に重要な方針です。ぜひ、収益を増やす経営を続けてください。
2024年の住宅着工統計がリーマンショック以来の80万戸割れ
2024年の新設住宅着工戸数は持家、貸家、分譲マンションを合わせた全体で約79万戸となり、リーマンショック以来15年ぶりに80万戸を下回りました。このうち貸家(賃貸住宅)の着工戸数は34万2,044戸(前年比0.5%減)、着工床面積は16,098千㎡(同2.3%減)と2年連続の減少となりました。
次に各地域の貸家着工戸数を元にトレンドを見ていきます。

地域別では、首都圏で東京都が65,433戸(前年比6.9%減)と減少する一方、千葉県(19,411戸、同12.0%増)、神奈川県(27,044戸、同6.9%増)、埼玉県(20,258戸、同5.3%増)と周辺県が好調です。
関東圏の賃貸仲介業者によると、「分譲マンション価格の高騰により住宅購入を断念した層が賃貸市場に流入し、特にファミリー向け賃貸住宅の需要が増加している」とのことです。
この需要増加を背景に、都内のある管理会社の調査では、2023年12月時点での東京23区内の募集家賃が2020年比で平均13%も上昇していることが明らかになっています。
CHECK1:建築費の高騰が住宅着工数減少の主因に
住宅着工数の減少は建築費の高騰が大きな要因とみられます。
木造住宅の建築費はコロナ前と比べて15.1%上昇し、建設業の就業者数は1997年の685万人から2024年には485万人まで減少。国が定める2024年度の建設労務単価は前年度比5%超の賃上げが予定されており、このような建築費高騰が続けば、ますます「建て控え」が増加しそうです。
また、中期的なトレンドにおいても日本の住宅市場は大きな転換点を迎えています。
CHECK2:世帯数減少と単身世帯の増加が進行
2023年を境に世帯数は減少に転じ、2040年までに5%程度減少する見通しです。特に単身世帯が全体の4割近くまで増える一方、「夫婦と子供」世帯は2割程度まで減少する予測です。こうした人口動態の変化を背景に、2025年以降も着工数の減少が継続すると予想されます。
全体で単身世帯が増加する中、コンパクトで機能的な物件への需要が高まるとみられます。特に都市部では、在宅勤務対応の設備(作業スペース、高速通信環境)を備えた物件の人気が増すでしょう。
また人口流入が続く首都圏周辺県や大阪、京都などの大都市、半導体産業が集積する熊本や観光需要が高く世帯数の増加が続く沖縄など、特定の成長分野を抱える地域では今後も賃貸需要が堅調に推移する一方、人口減少が著しい地方では空室率の上昇と家賃の下落圧力が強まることが予想されます。
CHECK3:入居者ニーズを捉えた戦略的投資が鍵に
こうした構造的な変化の中、これまで以上に入居者の好みを重視した戦略的な投資が重要になりそうです。
ある調査では、省エネ基準を満たす物件は入居率が平均8%以上高くなるというデータもあります。燃料費の高騰を受けて年々重くなる光熱費負担に敏感な入居者はますます増加しそうです。こうした動きを意識しながら、補助金制度を活用したリノベーションなどを念頭に物件の価値向上が求められるでしょう。
これからの賃貸住宅経営は、地域の特性を踏まえ、入居者のニーズを抑えた投資判断がこれまで以上に重要となるのは間違いなさそうです。
騒音トラブルはこう対処!管理会社の粘り強い対応とは?
繁忙期が終わると賃貸管理スタッフには、新しい入居者さんに快適に暮らしていただくための業務が始まります。その中でも、初めて共同住宅で暮らしたときに起きやすいトラブルとして「音の問題」があります。
先日、オーナー様から「入居者のAさんから、夜うるさくて眠れないと相談があった」と連絡を受けました。一口に騒音トラブルと言っても、「1.生活音が原因の騒音」「2.設備が原因の騒音」「3.入居者の迷惑行為による騒音」などいろいろなケースがあり、対応方法も異なります。
今回はその中の「生活音が原因の騒音」を取り上げ、私たち管理スタッフがどのように対応したかをレポートします。
解決のポイントは着地点を明確にする
騒音トラブルを解決する際は、最終的な着地点(解決したイメージ)を想定します。たとえば漏水トラブルは「漏水が止まる」ことが着地点ですが、騒音トラブルは音をゼロにすることは難しいので、着地点として
- 音を小さくする
- 音をなくす努力をアピールする
- 双方に建物の限界を理解してもらう
などのケースを想定しておきます。そうでないと際限の無い対応が続くことになってしまうのです。
管理会社がとるべき対応ステップ
具体的な方法として以下のようなステップを講じます。
- 音が受忍限度を超えているか現地で確認する
- (超えている時は)注意を促す文書を全戸に配布する
- 苦情元に経過を報告する
- 音が改善されない場合は騒音元を訪問しお願いをする
- それでも改善しない場合は訪問して注意する
この作業を根気よく繰り返すことになります。
現状把握から根気強い対応まで
Aさんに詳細を聞いたところ「ほとんど毎日、夜10時頃になると上の部屋から足音がドンドン響き11時過ぎまでつづく」とのことでした。実際に聞いてみると、上階の住人の足音がたしかに響くような音であると判断しました。上階は新しく入居した大柄の独身男性なのですが、10時過ぎという時間帯も問題です。
さっそく、注意を促す文書を全戸に配布しました。文書に、騒音の曜日、時間、音の種類を詳しく記すことで、騒音元に「自分のこと?」と気づいてほしい、という狙いがあります。しかし、1週間程度の様子を見た後にAさんに確認すると、夜の足音は改善されていないようなので、騒音元に直接訪問して「夜間の足音に関するお問い合わせがありまして…、もし心当たりがあれば、気をつけていただけると助かります」とお願いしました。
多くの場合、「そんなに響くと思わなかった」と気づいていただくことで状況は改善します。 Aさんにもその経緯を説明することで納得していただけることもあります。
しかし今回は、一度の依頼でAさんの納得が得られませんでしたので、騒音元に根気よく注意とお願いをし続けるうちに、上階の方も「踵(かかと)で歩かない、夜はスリッパを脱ぐ」など具体的な対策を講じてくださり、Aさんからの苦情は減っていきました。
こうして足音の問題は落ち着き、Aさんも「音が小さくなって助かりました。ありがとうございました」と穏やかにお話しくださいました。もちろん、音の感じ方には個人差があるため、100%の解決が難しい場合もありますが、「真摯に耳を傾け、根気強く対応する」という姿勢がAさんの満足につながったのだと思います。
騒音トラブル対応の限界と管理会社の役割
さて、今回のようにうまく事が運べないときもあります。たとえば、まったく注意を聞こうとしない住人に対しては、根気強く訪問を繰り返した後に退去をお願いすることもあります。(もちろん、強制的に退去させることは難しいのですが)。
あるいは騒音が改善されていても、「まだ音が聞こえる」と過剰反応を続ける苦情元の入居者さんにお部屋を替えていただくようお願いしたことも、過去にはあったようです。
音が「受忍限度を超えているか?」を現地で確認することの難しさもあります。スタッフが確認して、「これは限度内だな」と判断した時は、建物構造の限界について納得いただかなければなりません。
しかし物音と言っても、足音は生活するうえで必ず聞こえるものですが、物を叩いたり擦る音は通常ではありませんので、音の大小にかかわらず注意の対象になります。
そして、上下の方がそろって初めての共同住宅のケースでは、上階の方は「そんなに音は響かない」と思っていて、下にお住いの方は、初めて聞く他人の音に神経をとがらせてしまう、という行き違いが起こりやすいのです。
私たち管理スタッフは、今回のような「生活音」によるトラブルでは、その内容を正確に把握し、双方の主張に耳を傾けることを不可欠としています。そして、「管理会社はここまで対応してくれる」と感じていただけるように努めてまいります。
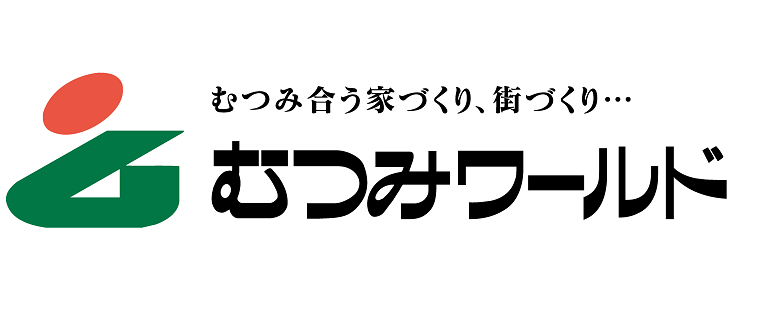
- Tags
- 人気のタグ
- Rerated
- 関連記事