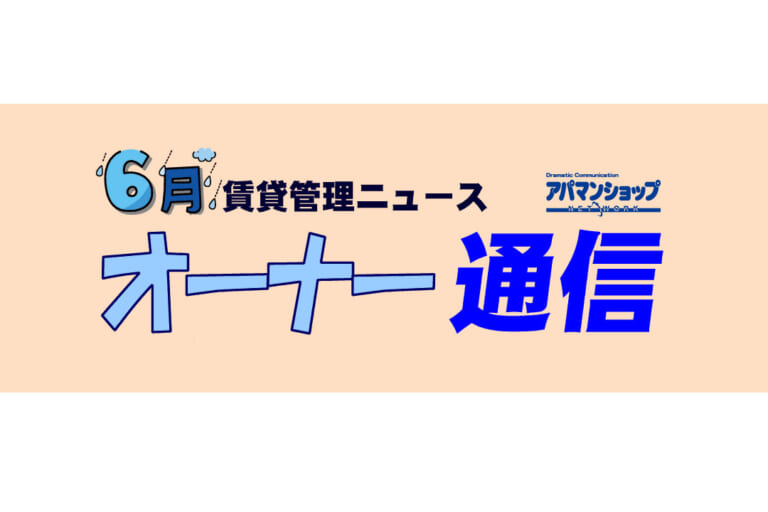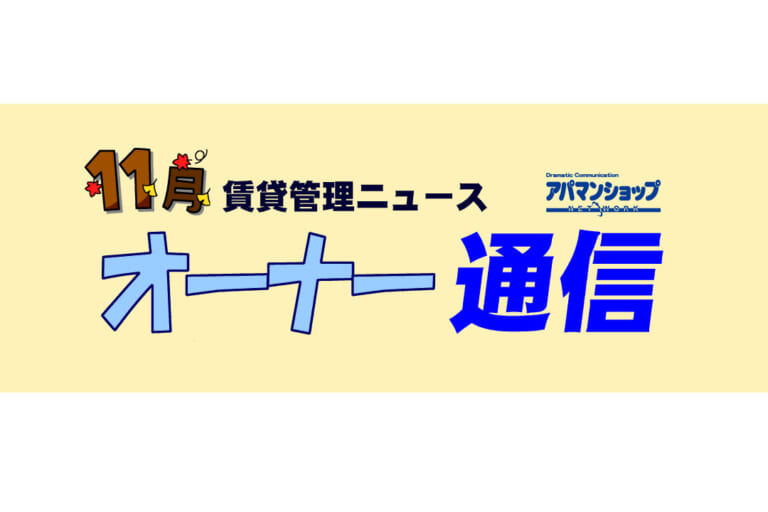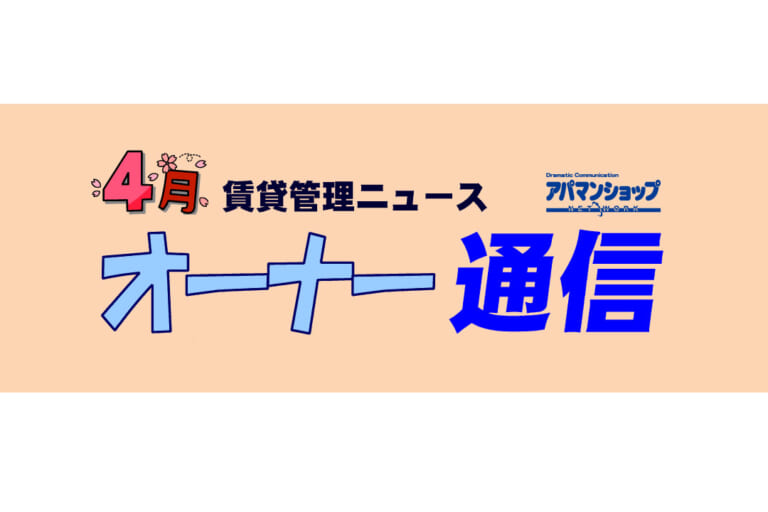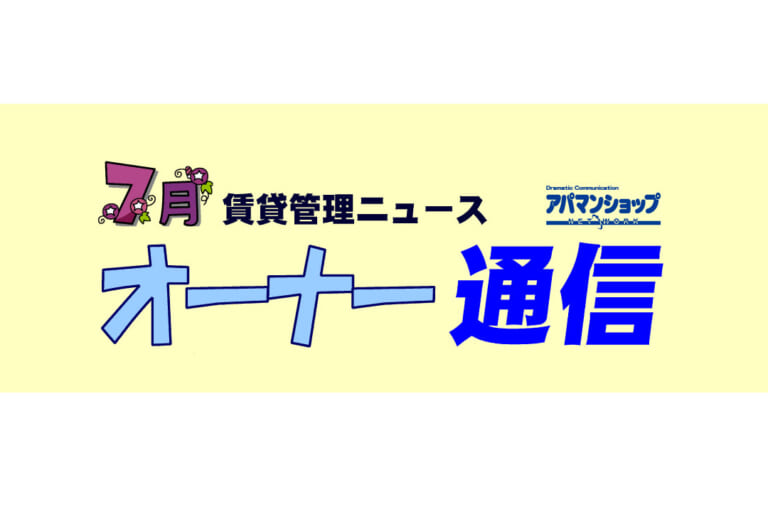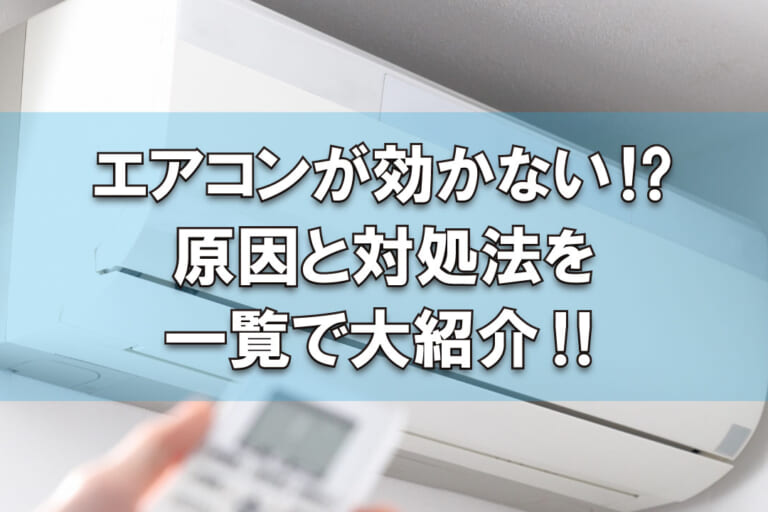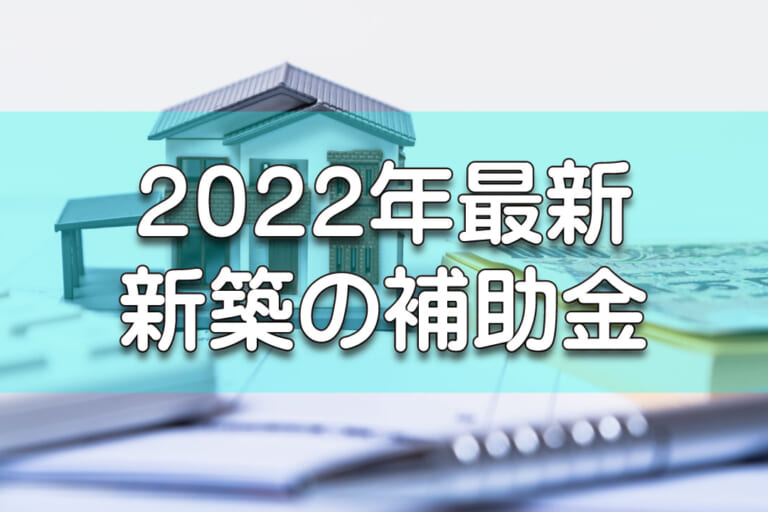- 2025.05.06
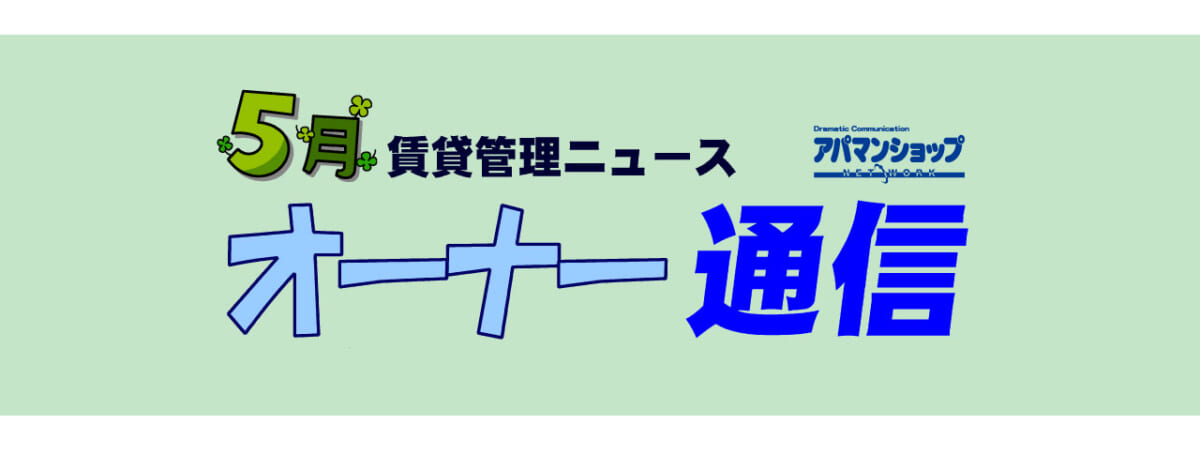
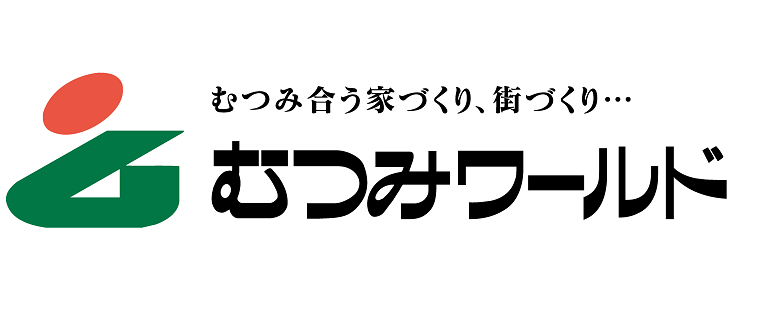
地震災害に対してオーナーが準備できること
立地のリスクと避難計画を知る
同じ地域の建物でも立地によって災害の危険度は異なります。それを知ることができるのがハザードマップです。ハザードマップとは、自然災害で想定される危険な場所や、避難経路・避難場所の情報を地図上にまとめたものです。地震・洪水・土砂災害などの種別ごとに作られていて、市区町村役場のホームページ、国土交通省のポータルサイトで入手することができます。
具体的には、国交省の「ハザードマップポータルサイト」から、全国自治体が作成したハザードマップへのリンクを集めた「わがまちハザードマップ」が閲覧できます。また国交省が作成した「重ねるハザードマップ」でも、洪水、土砂災害、津波、高潮など複数の災害リスクを地図上で重ね合わせて見ることができます。
これらは災害リスクを減らす上で役立つ資料なのですが、住民の認知度は高くなく、ある調査では約半数が「存在を知らない」「避難の参考にしていない」と回答した例もあるようです。オーナー様にご覧いただくことで、ご自宅や賃貸物件の災害リスクの現状を知ることができます。
さらに、ハザードマップを基に作成された「防災マップ」には、いざ自然災害が発生した時の行動計画が示されていて、避難経路や避難所の位置、避難所までの所要時間などが記載されています。この2つの資料を把握するとともに、入居者にも周知しておくことが災害被害に対する準備の第一歩となります。
賃貸物件の耐震診断と耐震補強
もし、ご所有の賃貸物件が新築および築浅で、建築基準を満たして建てられているなら、たとえ災害に遭ったとしても、損害賠償されるリスクは低いでしょう。しかし、築年数が10年20年30年と経過している場合は、建物と設備は当然に老朽化していますし、法律による基準が改正されている場合もあるので、リスク回避のための確認が必要になります。
その確認の方法として耐震診断があります。この費用については、全国の殆どの自治体で補助事業(補助金制度)が実施されています。また耐震診断の補助金制度と共に、認定を受けた建築物の耐震改修工事費用の補助が受けられる制度も年々整いつつあります。
地方自治体によって様々な規定や条件が定められていて、対象建物や金額は一定ではありませんが、窓口に相談することで知ることができます。
「新築時の建築基準を満たしていればよいのでは?」という疑問についても解説しておきましょう。1995年に施行された耐震改修促進法では、一定規模以上の建物を「特定建築物(賃貸住宅では3階以上で1000㎡以上)」とし、その所有者は建築物が「現行の耐震基準と同等以上の耐震性能」を確保するよう耐震改修する、という努力義務が求められています。
この努力を怠っていた場合に、地震災害による建物倒壊や落下による被害者から訴えられたときの損害賠償リスクはゼロとは断定できないでしょう。このように賃貸経営にリスクマネジメントは必須ですが、耐震診断と耐震改修を行うかどうかは、その可能性とコストを考えて、個々に判断して決めるしかありません。まずは自治体の補助金制度について検討するところからスタートとなります。
その他に準備しておくこと
いざ災害が起こった時は誰でも慌ててしまうものです。それに備えて必要な情報はメモにして、目立つところに掲示しておくとよいと思います。まずは、固定電話や携帯電話がつながりにくくなったときのための通信手段です。「災害用伝言サービス」として
- 災害用伝言ダイヤル(171)
- 災害用伝言板(web171)
- 携帯各社の伝言板などが用意されています。
インターネットが利用できるように、00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)という 無料Wi-Fiも提供されるようです。
実際に、賃貸建物の被害状況や入居者の現況を調査するのは管理会社になりますが、そのためにも災害時に連絡を取り合う方法を確認しておきましょう。最後に、地震災害に対してオーナーが準備できることとして「保険加入の検討」があります。
賃借人の孤独死で2か月半放置。賃借人の相続人に損害賠償請求できるのか?
今回は、賃借物件内で発生した自殺や孤独死に伴う損害賠償請求の可否について、裁判例をもとに解説します。
まずは孤独死ではなく、賃借物件内で自殺事件が発生した場合、賃貸人は将来の賃料の低下等に伴う損害を請求できるか、について考えてみましょう。この場合には、今後の賃貸で「事故物件」と扱われることになり賃料低下を余儀なくされてしまう場合が多いです。
賃貸人としては賃借人の相続人に対して、賃料低下分について損害賠償請求を検討することになります。どの程度認められるかという問題については
- 当初1年間は賃料全額
- その後の2年間は賃料半額程度
の請求を認めた都心のワンルームマンションの事例(東京地裁平成27年9月28日判決)などがあり、賃借人の自殺のケースでは損害賠償基準が実務上も確立していると考えられています。
つぎは、賃借物件内で孤独死が発生して長期間放置された場合はどうなるか、について考えます。この場合でも自殺と同様に、賃借人の相続人に対して将来の賃料の低下等に伴う損害を請求できるのでしょうか? この点について判断した裁判例が東京地方裁判所平成29年9月15日判決です。
この裁判の概要は以下のとおりです。
ある日、賃貸人に賃貸マンション(賃料は月額10万円)の一室から異臭がするという近隣住民からの通報があった。室内の賃借人が死亡していることが予想されたため、賃借人の家族と警察官に立ち会ってもらい、ドアを開けて当該室内に立ち入ったところ、賃借人が借室内の布団の中で死亡した状態(死因不明)で発見された。
死亡推定日時は発見された日の2か月半ほど前であり、布団から液体が床に染み出しているような状態だった。遺体が2か月半放置されたことにより大掛かりな原状回復が必要となり、その費用として50万円以上が計上された。
賃貸人は賃借人の相続人(賃借人の両親)に対し、上記の損害のほか、今後は長期間の空室が続く蓋然性が高いとして1年間の賃料の半額を損害として請求した。
裁判所は損害賠償請求を否定して賃貸人の訴えを退けました。
この事案の法律上の問題は、賃借人が室内で死亡し、その発見が遅れてしまったとき、生前の賃借人に、善良な管理者としての注意義務について違反があったか否か、ということになります。この点について裁判所は賃借人の義務違反を認めませんでした。理由は以下のとおりです。
賃借人の死因は不明であり自殺したとは認められない。また賃借人が生前持病を抱えていたなどの事情はうかがわれないから、賃借人が、当時、自分が病気で死亡することを認識していたとは考えられず、また、そのことを予見することができたとも認められない。
以上によれば、賃借人に善管注意義務違反があったとは認められず、同違反を前提とする損害賠償請求には理由がない。したがって、賃借人の相続人も損害賠償義務を負わない。
この裁判所の考え方によれば賃借人が賃借物件内で自然死した場合
- 賃借人が生死に関わる持病を抱えていたこと
- 上記によって突然死もしくは居室内で死に至ることが十分に予見できたこと
このような事情が存在しない限りは、長期間に放置されていた場合でも、賃借人の善管注意義務違反は認められない、ということになると考えられます。したがって、賃借人の自然死(及び発見の遅れ)の場合には、相続人に対して将来の減収分を請求することは難しいと言わざるを得ません。この「生死にかかわる持病」について、判決文などで基準が明示されたり特定はされていません。この点は、社会通念や社会常識から判断されることになります。
令和3年10月8日に、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が国土交通省により策定されました。このガイドラインによると、老衰や病死などの自然死(孤独死を含む)は原則として告知する必要はないとされています。今まで曖昧に運用されていたことが解消されることで貸主有利になったと言えます。
一方で、孤独死から長期間放置されていた場合は3年間は告知すべき、と明示されたことは貸主にとっては不利に働くことになります。これにより、賃貸人に将来の減収が生じる可能性はより高くなったといえます。今後の裁判事例では、賃借人の善管注意義務違反の判断に影響が生じる可能性(より義務違反を認め得る方向になる可能性)もあると思われます。
地価上昇の背景から読み解く、これからの賃貸経営
2025年の公示地価が発表され、全国平均で全用途+2.7%の上昇となりました。住宅地は+2.1%、商業地+3.9%、工業地+4.8%と、いずれも前年を上回る上昇率。特に東京圏では住宅地+4.2%、商業地は+8.2%と、都市部を中心に力強い回復が見られます。
一方で、今回の地価上昇は都市部に限らず、地方圏にも広がりを見せている点が特徴です。「自分の物件があるエリアではどうか?」と、オーナーの皆様にとっても今後の経営を考える重要なヒントになりそうです。
子育て支援と住環境の充実が住宅需要を引き上げる
最も顕著な例は、千葉県流山市。TX(つくばエクスプレス)沿線の利便性に加え、保育所の整備や子育て施策の充実が高く評価され、住宅地の上昇率は+13.6%と県内トップを記録しました。
兵庫県明石市でも、給食費の無償化や医療費助成制度などの積極的な支援策が奏功。8年連続で地価が上昇し、2025年は+4.1%となっています。岐阜県岐南町も同様に、教育や住環境の整備により若い世代の転入が増加。住宅地の価格は+1.2%を記録しています。
これらの地域では、新築需要だけでなく、既存の賃貸住宅にも追い風が吹いています。若年層の流入は長期的な居住にもつながりやすく、空室対策や設備投資の優先順位にも影響を与えるでしょう。
半導体工場の立地が地域経済と賃貸市場を動かす
北海道千歳市では、大手半導体メーカー「ラピダス」の工場建設が進んでおり、関連企業の進出や建設ラッシュによって商業地が+37.8%と全国最高の上昇率を記録しました。
九州でも同様の傾向が見られます。福岡県久留米市では、住宅地+5.5%、工業地+5.2%と需要の高まりが数字に表れています。工場労働者や技術者の居住ニーズ、さらにはそれを支えるサービス業の活性化が、地域全体の不動産市場に波及しています。
このような地域では、従業員向けの中長期賃貸住宅や社宅ニーズも増え、物件の種類や間取りによっては家賃見直しのタイミングになる可能性もあるでしょう。
インバウンド回復が観光地に地価を再浮上させる
コロナ禍で停滞していた観光業も、インバウンドの復活により再び注目を集めています。北海道富良野市の北の峰地区では、住宅地が+31.3%と全国トップの上昇率に。外国人観光客の増加が別荘やホテル用地の需要を押し上げた結果です。
長野県白馬村では、国内外からのスキー客による別荘・コンドミニアム需要が堅調で、住宅地+19.8%、商業地+33.0%の上昇。兵庫県豊岡市(城崎温泉)や大分県別府市などでも、観光客の回復とともに宿泊施設や飲食店用地の需要が高まり、商業地が2桁の上昇を見せました。
観光地の地価上昇は、短期滞在者向けの賃貸需要や宿泊施設の運用にも影響を与える要因となっています。
地価上昇をどう読むか?これからの賃貸経営への示唆
このように地価が上昇している背景には、“人の動き”があります。住みやすさを求める若年層、産業誘致に伴う労働人口、観光回復による短期滞在者──それぞれの動きが、賃貸ニーズに直結しています。
大切なのは、単に「上がっている・下がっている」を知るだけではなく、その背景を理解し、「自分の物件にとってはどんな影響があるのか?」を読み解く視点です。
自身の物件エリアを見直すことから始めよう
そして今こそ、自身の物件がある地域の経済状況・人口動向・産業立地などを確認し、賃貸需要の見通しを立てることが大切です。
一方で注意したいのは、建築コストの上昇や資材価格の高騰によって、仮に新築や再投資を考えても、以前よりも大きな資金が必要になること。投資利回りが思ったほど出ない可能性もあるため、慎重なシミュレーションが求められます。
今すぐに売却や購入を決める必要はありませんが、まずは地価の動きから「自分の物件はどうか?」を考えるところから、賃貸経営の次の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
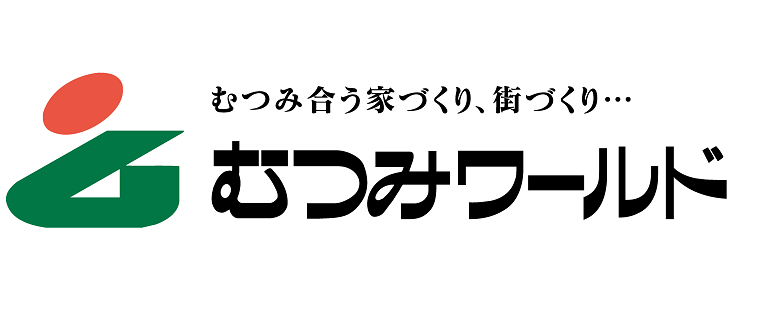
- Tags
- 人気のタグ
- Rerated
- 関連記事