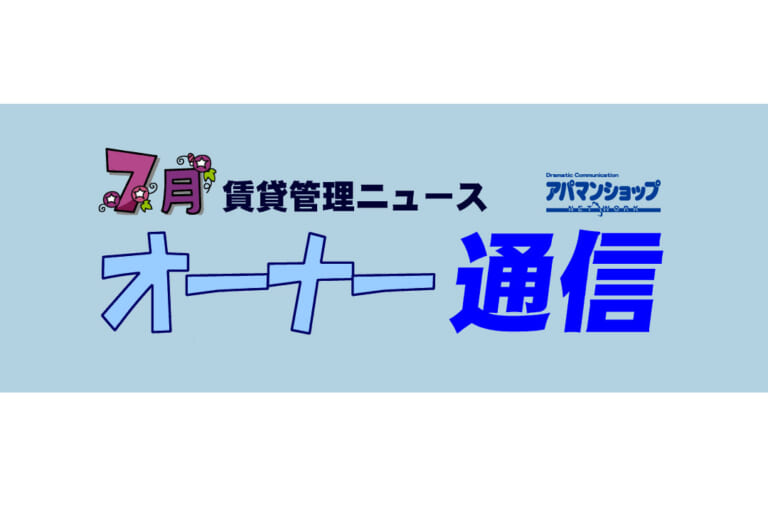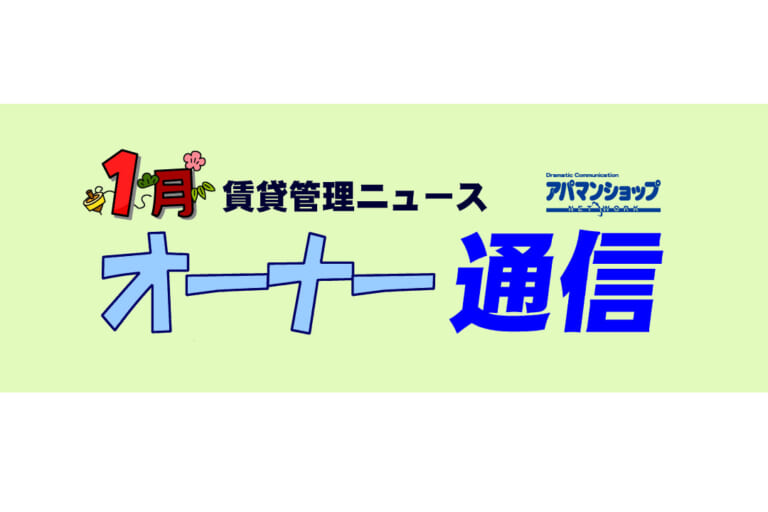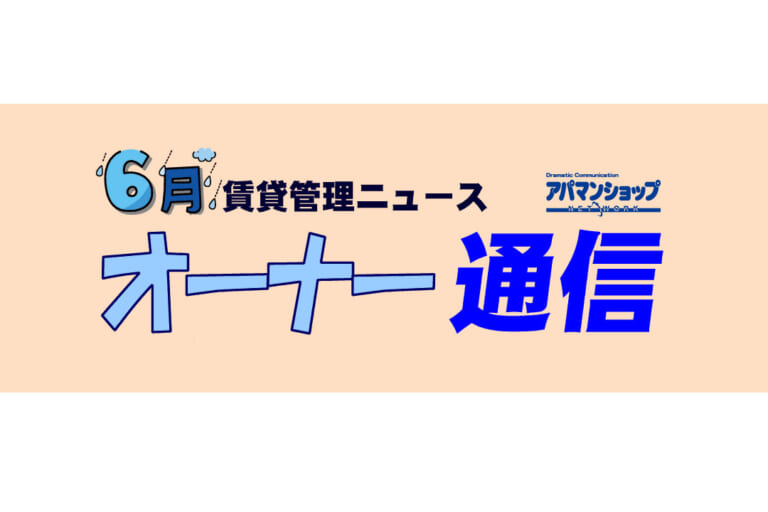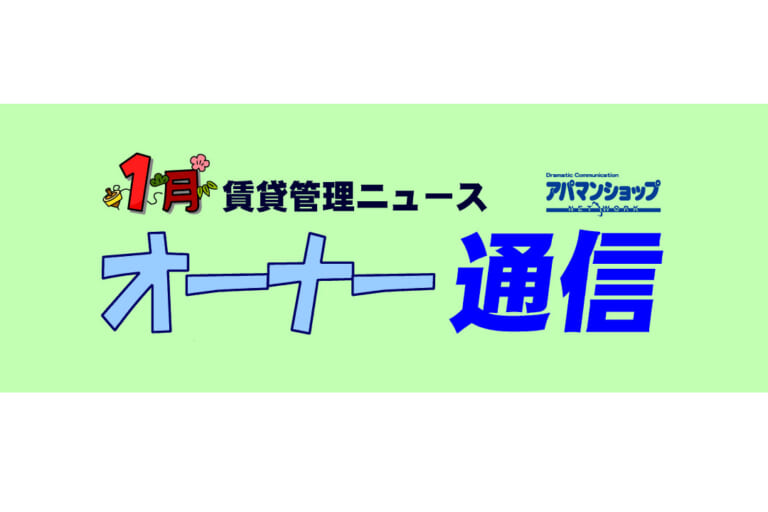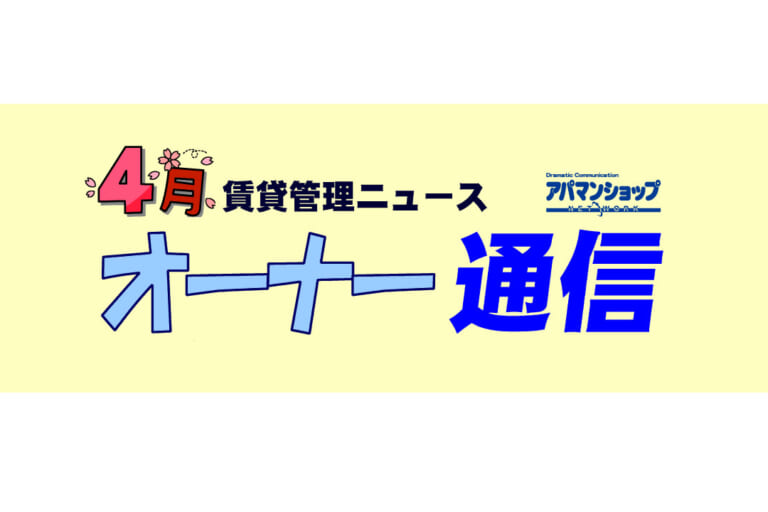- 2025.08.05
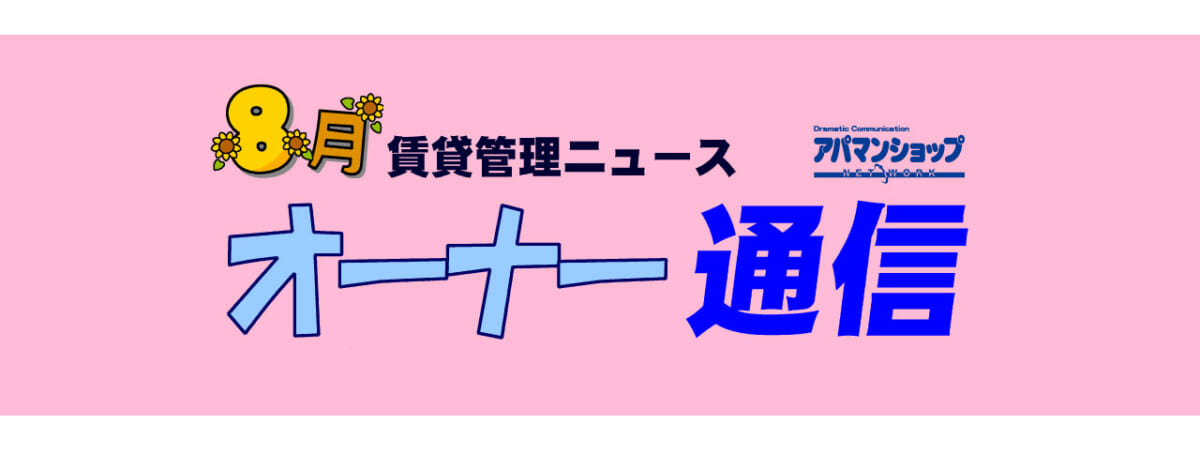
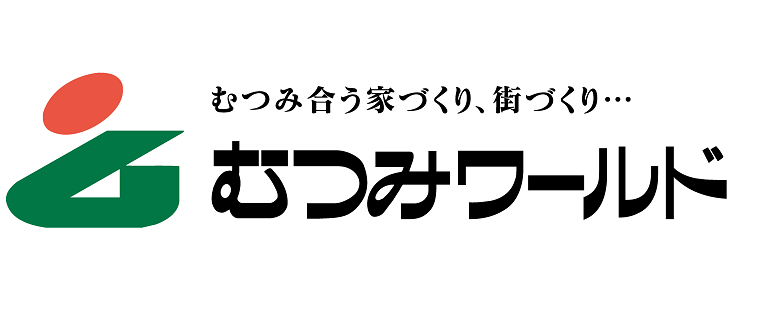
見落としていませんか?外壁点検が資産価値と満室経営の決め手に
Q、築22年30世帯のアパートを所有しています。外壁はサイディングですが、まだ一度も手入れしていないので、最近は塗装やコーキングが劣化しているように感じます。特に雨漏りしているわけではないので多額の経費をかけることに躊躇しています。アドバイスをお願いいたします。
A、今回はご質問に答えながら、賃貸物件の外壁の耐久性と点検の重要性についてお伝えします。外壁はいつも雨風の影響を受けているため、年数の経過により必ず劣化します。ご質問されたオーナー様が所有している塗装系の
外壁の場合、一般的に外壁塗装の耐久年数は、使用する塗料によって異なりますが、ウレタン系で7~10年、シリコン系で10~15年、フッ素系なら15~20年程度が目安です。しかし、これは「耐用年数」であって「保証期間」ではありません。実際の劣化は、立地環境や気候条件によって早まることもあるのです。
外壁劣化がもたらす賃貸経営への影響
ここで大事なのは、見た目だけでは正確な問題が把握できないということです。外壁が劣化すると、見えない箇所で建物内部へ雨水の侵入につながり、構造体の腐食やシロアリの発生リスクを高めます。こうした症状が進行すると、部分的な補修では済まず、数百万円単位の大規模修繕が必要になるケースもあります。それだけでなく、外壁の見た目は物件の第一印象を左右します。入居希望者が「この物件、ちょっと古くさそう…」と感じれば、それだけで内見をスキップされるかもしれません。 つまり、外壁の美観は、入居率を左右する重要な要素なのです。どれだけ室内をリフォームしても、外観で“足切り”されてしまっては意味がありません。このように外壁の劣化は、建物の寿命を縮め、賃貸経営の収益性を脅かすリスクです。反対に、外壁が美しく維持されていれば、「手入れが行き届いた物件」という印象を与え、入居希望者にも安心感をもたらします。結果として、長期的な資産価値の維持、そして空室リスクの低減にもつながります。
点検のタイミングとチェック項目
外壁の点検のタイミングとしてよく勧められているのは「築10年を過ぎたら5年ごとに点検」、そして「20年を超えたら3年ごとに点検」を目安にすること。もちろん、異常を感じたら早急にプロの診断を依頼すべきです。
ご自身で点検される時は、以下の点をチェックしてください。
- 写真リストひび割れ(クラック)
- 塗膜の劣化(チョーキング現象)
- コーキング(シーリング)の劣化
- 塗装の色あせ・はがれ
- カビ・コケ・藻の発生
- 浮きや剥離
- 金属部分のサビ・腐食
- 外壁材の目地・つなぎ目のズレや変形
今回のオーナー様は、「塗装やコーキングが劣化しているように感じる」とのことなので、以下の事例のような現象がおきていないか、チェックしてみてください。
正常〇:チョーキングが手につかない
劣化✖:チョーキングが手につく
劣化✖:外壁が劣化した状態
正常〇:コーキングに弾力がある✖
劣化✖:固く亀裂が生じる
いかがでしょうか。「まだ壊れてないから大丈夫」と補修を先延ばししがちですが、それが落とし穴になることがあります。実際に雨漏りが起きてしまってから修繕するのと、コーキングのひび割れ程度の段階で補修するのとでは、費用も工事期間も大きく異なることは理解いただけるでしょう。
外壁点検は「収益を守るための投資」
外壁点検と補修に多額の費用がかかることは事実ですが、視点を変えれば「資産価値を維持し、家賃を守る投資」です。特に、築20年以降の物件は、修繕費が増えるタイミングと家賃収入が落ちる時期が重なるため、計画的なメンテナンスを行うことで賃貸経営の収益を守ることができます。収支計画を長期で立て、必要な箇所に的確なメンテナンスを実施すれば、将来的な出費の平準化にもつながります。
外壁管理は、満室経営への第一歩
「まだ使える」「まだキレイだから」と後回しにすることは簡単です。しかし、収益物件の価値は「見えないところでの管理努力」によって決まります。外壁点検や補修は、まさにその代表的なものです。 清潔感と管理の行き届いた印象を与える外観、そして構造の安全性。これらを守ることが、満室経営につながる重要な土台なのではないでしょうか。
「小規模宅地等の特例」を活かすには
相続対策の中でも、不動産オーナーに大きな影響を与えるのが「小規模宅地等の特例」です。
この制度は大きく分けて3つに分類されます。
利用区分:上限面積 減額割合
①特定居住用宅地 (自宅):330㎡ 80%
②特定事業用宅地(店舗・工場など、自己で事業に使用している土地):400㎡ 80%
③貸付事業用宅(アパート・駐車場など、第三者に貸し付けている土地):200㎡ 50%
いずれも、条件を満たして適切に活用すれば、相続税評価額を大幅に引き下げることができます。 相続財産に一定規模の宅地等が含まれている場合には、数百万円から、場合によっては数千万円単位で相続税を抑えられる可能性もあります。
また①自宅などの特定居住用宅地と②店舗などの特定事業用宅地の両方に該当する場合は、併用が可能で、それ
ぞれの限度額まで適用可能です。
なお、特例の併用にあたっては、「どの宅地に何㎡まで適用できるか」という上限が決まっており、③アパートなど
の貸付事業用宅地が含まれるケースでは、①特定居住用宅地や②特定事業用宅地と異なる複雑な面積制限が設けられています。特例の効果を最大限に活かすためには、3つの中から「どれを選んで適用するか」「どこまで使うか」といった判断が求められます。
例えば評価額が非常に高い都市部のアパートが対象であれば③貸付事業用宅地を優先した方が有利になることもありますし、①特定居住用宅地と②特定事業用宅地だけを活用した方が結果的に節税額が大きくなるケースもあります。
このように組み合わせによって結果が大きく変わるため、最終的には税理士など専門家の試算を通じて判断する
ことが重要です。
地方オーナーでも「小規模宅地等の特例」を活かせる可能性がある?
小規模宅地等の特例は「対象面積の上限」があるため、「評価額が高くて面積の小さい都市部の土地」ほど制度の
メリットを活かしやすく、逆に「評価額が引くて広い地方の土地」では節税効果が限定的になりがちです。 しかし、ある工夫をすることでメリットを活かすことができる可能性があります。 それが、「等価交換(不動産交換特例)」という制度を活用する方法です。
そもそも「等価交換(不動産交換特例)」って何?
簡単にいうと、自分の持っている宅地等と、他人が持っている宅地等を“等価”で交換することです。
例えば■地方にある「坪単価が低く」て広い宅地等」(例:1000㎡、坪単価10万円)
■都市部にある「坪単価が高くて狭い宅地等」(例:200㎡、坪単価50万円)
を、価値が釣り合う形で交換することができます。
このとき、「不動産交換特例」を使えば、通常の売買であれば発生する譲渡所得税(売却益に対して課税される所得税・住民税)を、その時点では課税せず、将来的に売却などを行ったときまで繰り延べることができる仕組みです。つまり、課税が免除されるわけではありませんが、現時点で納税を回避でき、資金繰りや節税対策を柔軟に行える点が大きなメリットです。
現実的にできるの?
たしかに、実務上は「交換相手がいるか?」「税理士や専門家のサポートが必要か?」といったハードルがあります。しかし、将来の相続や資産承継を見据えて、“節税を意識した不動産の組み替え”を行うことは、納税負担を軽減しつつ、資産の収益性や流動性を高めるうえで非常に有効な戦略といえます。
小規模宅地等の特例が適用できないリスクに注意
「小規模宅地等の特例」は非常に有効な節税制度ですが、条件を満たしていなければ適用されません。特に近年は税務署による審査も厳しくなっており、単なる形式要件だけでなく、実際に賃貸事業が継続されているか、相続人に事業継続の意思があるかといった“実態”が重視される傾向にあります。 例えば、長期間の空室やリフォームなどで一時的に賃貸が停止していた場合、「実際に貸していなかった」と判断されることがあります。また、土地が法人名義である場合は制度の対象外となり、さらに相続発生後すぐに売却や建物の解体を行った場合も、「継続利用の意思がなかった」とみなされ、特例が適用されない可能性があります。
「うちは問題ないだろう」と思っている方こそ、こうした細かな落とし穴には十分に注意が必要です。 相続は、準備次第で大きく結果が変わります。特例を活かすためにも、詳しく税理士さんに相談して今から備えておきましょう。
外国企業オーナー「家賃2.5倍」事件が教える教訓
東京都板橋区の築40年以上の1K賃貸マンションで、中国籍企業のオーナーが月額7万2500円の家賃を17万5000円に引き上げる通告を行い、エレベーター停止などの強硬手段に出ました。さらに無届けで民泊利用していたことも発覚。住民の約4割が退去または退去を決意し、問題は大きな波紋を広げました。円安・低金利を背景に外国人投資家の参入が増える中、今後の賃貸管理体制の見直しが求められています。
借地借家法に定められた「鉄壁の借主保護」
日本の借地借家法は借主を強力に保護しており、普通借家契約で家賃を値上げするには、 ①固定資産税等の税金の増加、②土地・建物価格の変動、③近隣との賃料比較、④経済事情の変動、と い っ た 要 件 の い ず れ か を 満 た し 、かつ社会通念上相当である必要があります。
今回の「家賃2.5倍値上げ」はこれらを満たさないので、認められない可能性が圧倒的に高いといえます。さらに
正当な理由なくして借主を退去させることも更新拒否することもできません。こうした強引な値上げや退去強要は、貸し手側の信用を損ない、長期的にはオーナーの収益機会を奪いかねません。
今回の事件を受け「海外では大幅な家賃の値上げは普通にある」といった解説もあったようですが、これは事
実と少し異なります。
実際、世界の主要都市・地域で「入居中の賃料を一気に2~3倍に上げる」ことは、制度的にも市場慣行としても例外的です。米国のニューヨーク市では年間2.75%、カリフォルニア州では「5%+消費者物価上昇率または10%の低い方」が上限として設定されており、ドイツでは3年間で20%を超える値上げが禁止されています。日本の借地借家法による保護水準は、国際的に見ても決して過剰とは言いきれないほどです。つまり、日本の制度は国際的にも突出して厳しいとは言えず、今回のような対応は国籍を問わず、利益追及に目がくらんだ素人オーナーの暴走と断じていいでしょう。
海外投資家増加の背景と売却時の注意点
日本の不動産には海外からの不動産投資が急増しています。最大の要因は円安と低金利環境です。海外投資家にとって割安となった日本の不動産への投資が活発化しており、国内オーナーの高齢化に伴う売却ニーズとマッチングしているのが現状です。ここで重要なのは、物件を売却する際のオーナーと仲介会社の努力です。売却時には、買い手に対して日本の賃貸住宅制度や法的規制、業界慣行について説明を行うようにしたいものです。また入居者に対して適切な管理体制を維持してくれる見込みがある人に売却するようにしてほしいところです。これは国籍を問わず、すべての物件売却において求められるものかもしれません。
業界全体の信頼性向上に向けて
今回のような強引な家賃値上げトラブルは、賃貸住宅業界全体のイメージを損なう恐れがあります。全国的な話題になったように、家賃の値上げに対する反発や関心は非常に高いです。これが、もっと継続的な社会問題にまで発展するようになれば、正当な家賃の値上げすらやりづらくなる可能性も考えられます。すでにネット上には「家賃の値上げは全て拒否できる」などの誤った情報も見受けられます。 しかし、これを機会と捉えることもできます。法律や制度への深い理解、地域社会との適切な関係、長期的視点に基づく経営姿勢などは、経験豊富なオーナーとして優位に立てる要素です。
板橋区の事件は、業界にとって痛い教訓となりました。しかし、この経験を活かし、不動産会社とオーナーがプロ
フェッショナルとしての自覚を持って経営に臨むことで、賃貸住宅業界の健全な発展が可能になるでしょう。言う
までもなく、すでに多くのオーナーが実践していることでもあります。しかし、これから多国籍など多様な背景を持つオーナーとの共存は避けられない現実です。だからこそ、経験あるオーナーが率先して業界の規範を示し、信頼される賃貸経営のあり方を追求していくことが求められています。
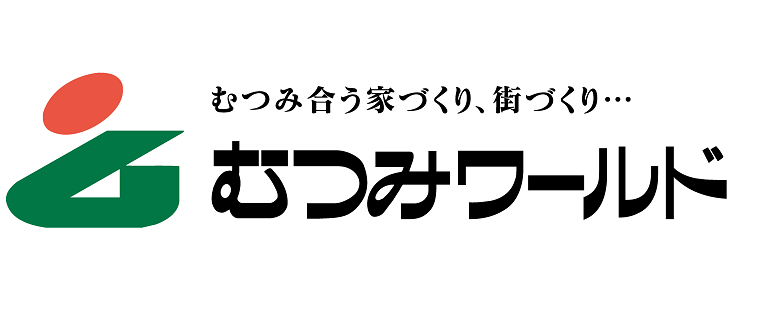
- Tags
- 人気のタグ
- Rerated
- 関連記事