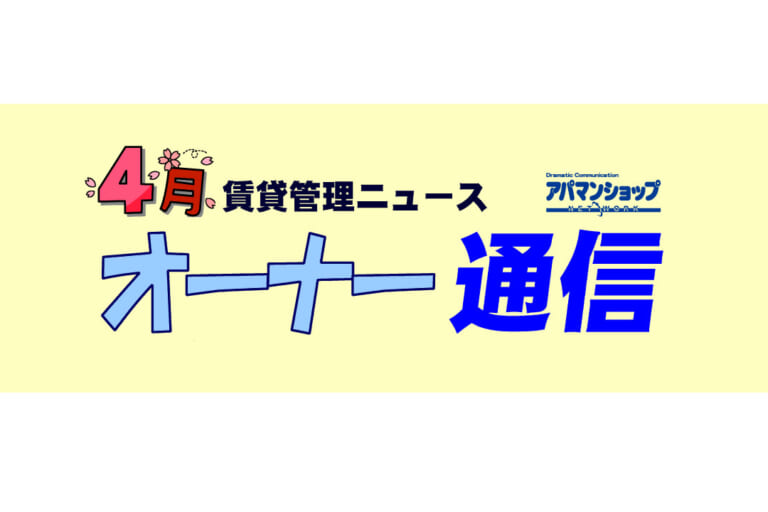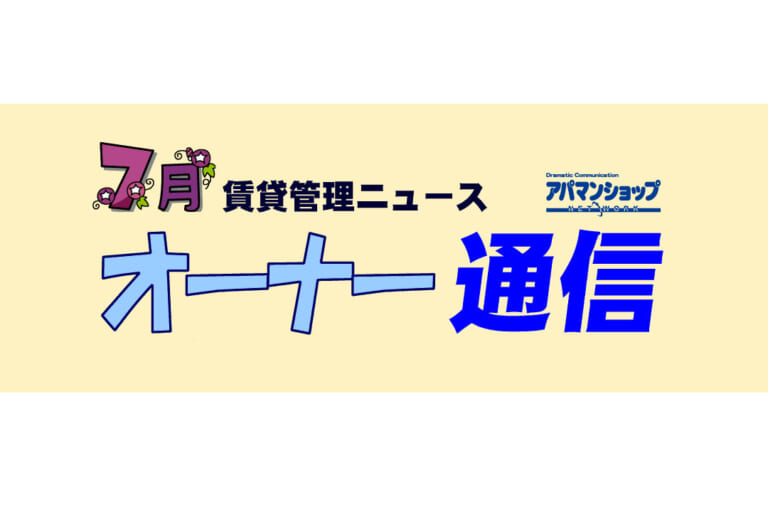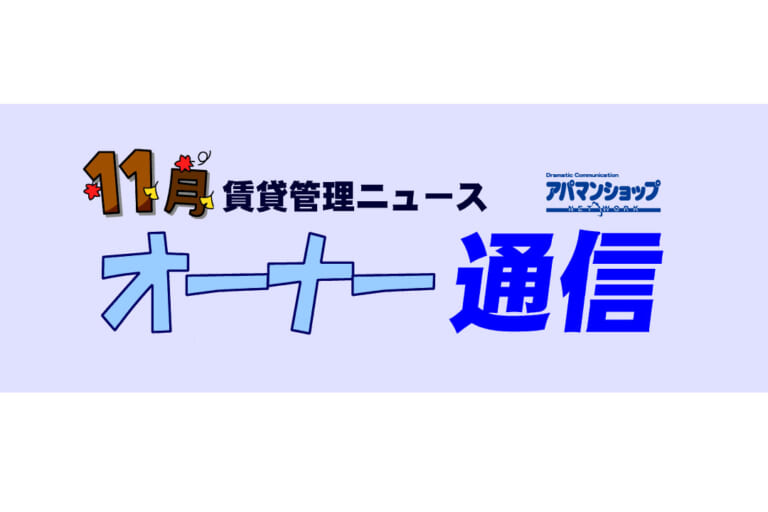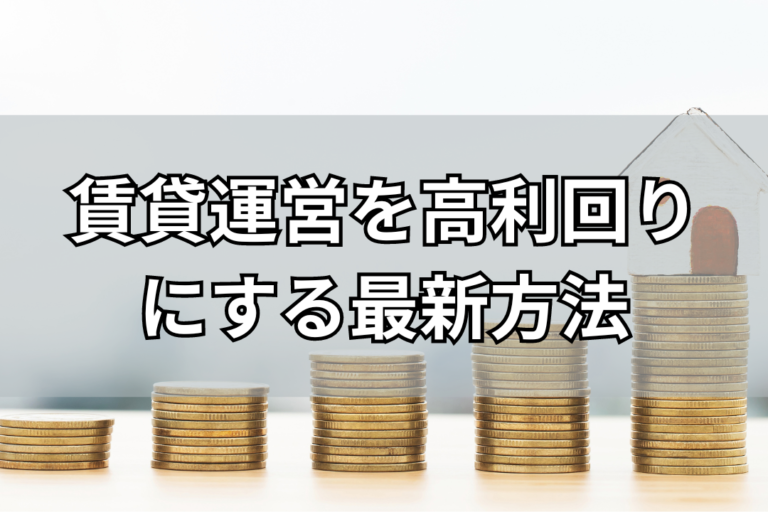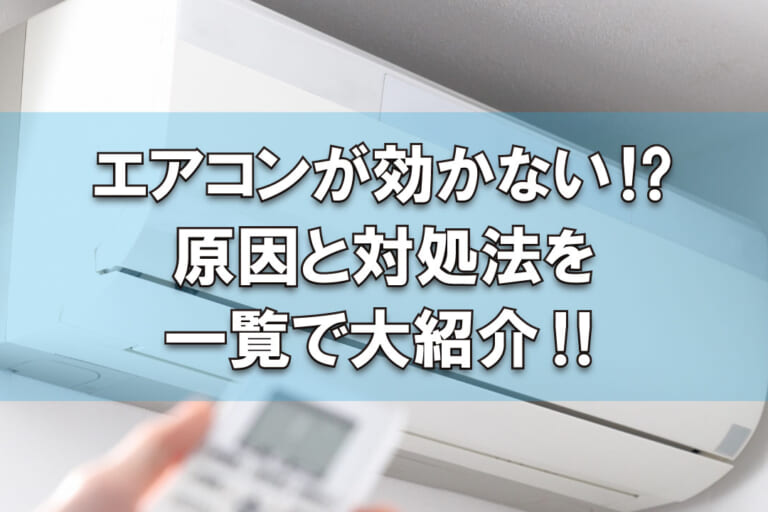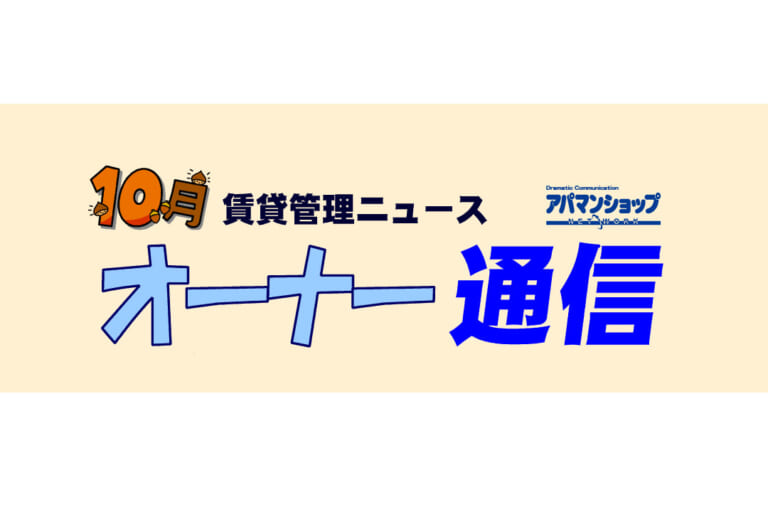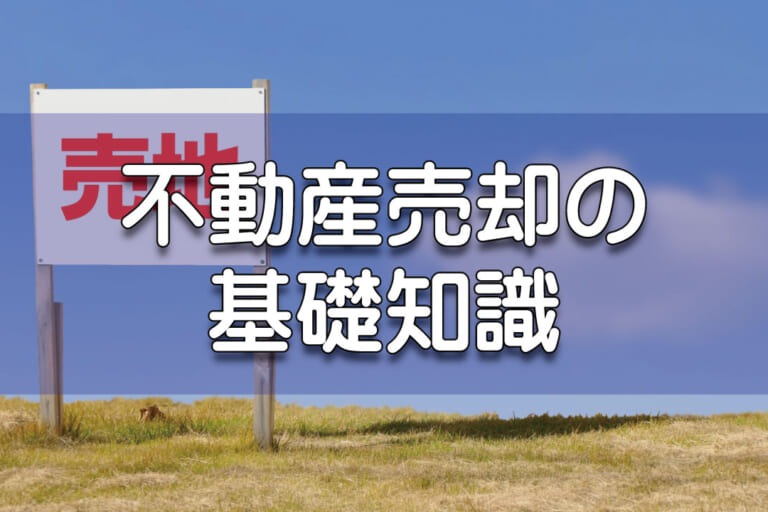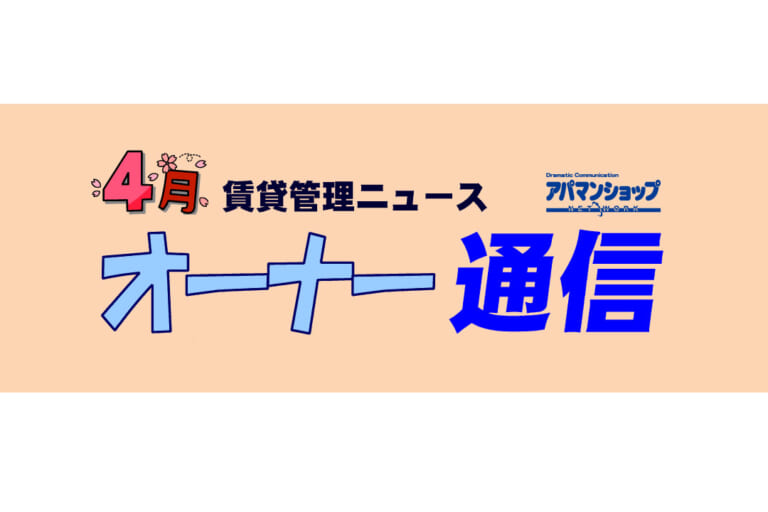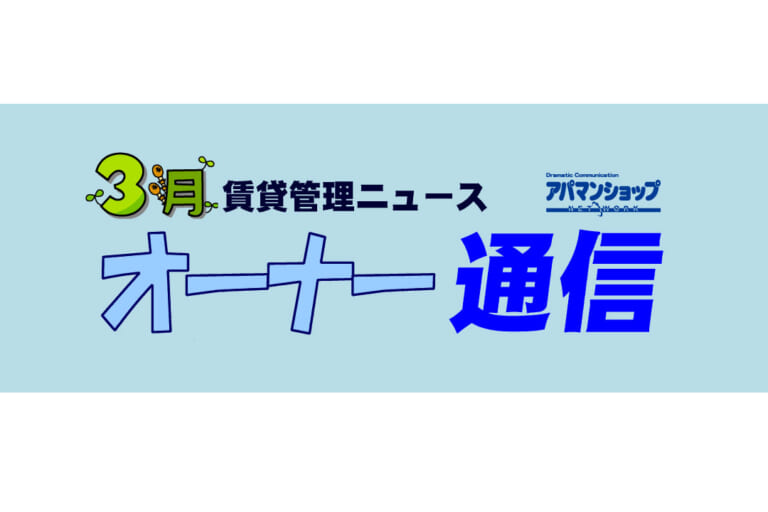- 2025.09.06
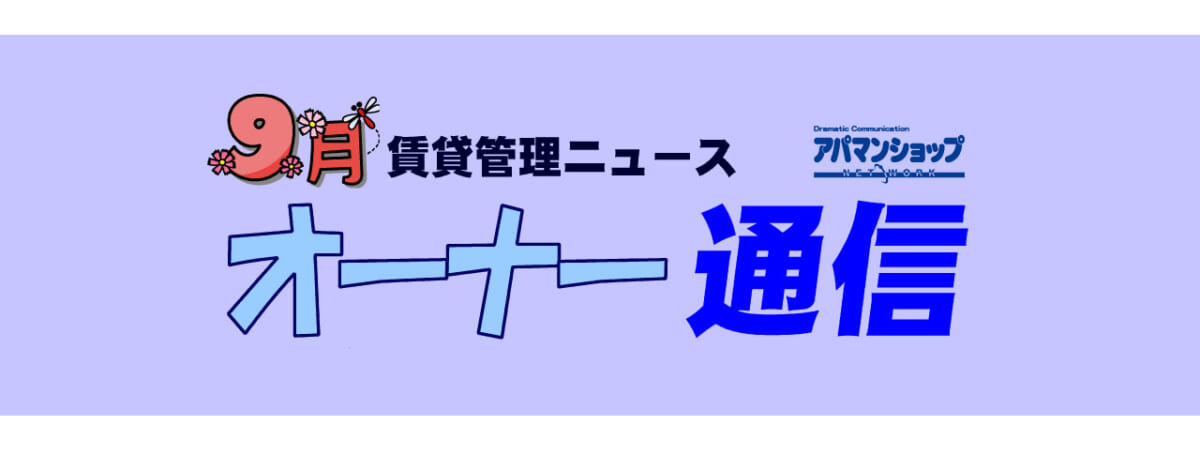
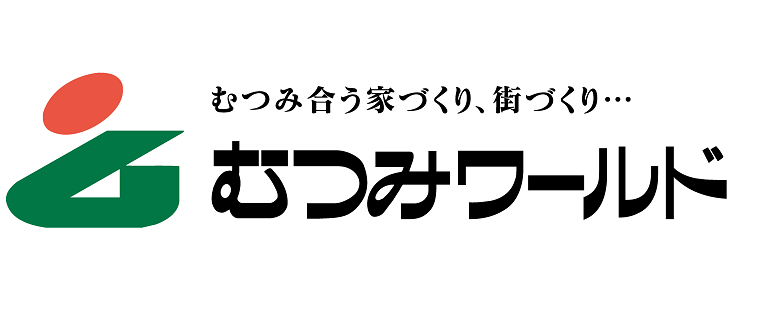
【第4回】地震が起きた時とその後にやるべきこと
震災が発生したときは、“まず自分と家族の身を守る”ことが最優先です。いざという時に自宅の中で身を守れる場所を決めているでしょうか? そして最初の揺れが収まったら、火の始末と出口の確保。その後の余震に備えつつ、このまま在宅避難を継続できるか、避難場所に移動する必要があるかを確認する、という手順になりますね。
さて、我が身の安全と避難住居が確保できたら、次は賃貸物件の現状を知るための行動になります。管理および募集を依頼している不動産会社に、電話や、その他に決められた方法で連絡して現地確認を依頼します。大混乱につき連絡がつかずに物件が近くの場合は、ご自身で現場に行くこともあるかもしれません(可能な限り不動産会社スタッフの同行が望ましいです)。ここからの作業は不動産会社が行うことですが、「災害時に貸主側がとるべき行動」という意味で知っておいて無駄にはならないと思います。この現地確認の目的は、
- 継続して住める状況か否か
- 修繕が必要な場所や危険箇所の特定
- 入居者の安否や避難状況
- 入居者へ危険箇所を周知
- 犯罪を防ぐための注意・対策
などです。
建物が余震で倒壊する危険性や、窓ガラスや建物の一部が落下する危険性などを判定します。これは「応急危険度判定士」という資格者が行います。2009年3月末時点で全国で102,610人の判定士が登録されています。(ボランティアで危険度判定を行います) ここで判定される被災度ランクは最終的に、「危険(赤)」、「要注意(黄)」、「調査済(緑)」の3段階になります。
「危険」、「要注意」の建物には立ち入らないようにしましょう。まだ避難していない入居者がいたら、避難に必要な情報を伝えて退去を促します。「調査済」の場合は、危険または要注意に該当しないので在宅避難が可能と判断できますが、留守で安否不明の部屋があったら、貸室玄関に「安否確認。避難先と連絡方法のご連絡を」などの張り紙をしておくとよいですね。
被災して一定期間が経過したあと
以降も、不動産会社と相談して進めることになりますが、賃貸建物に継続して住むことが困難な場合は、震災日をもって賃貸借契約を終了させることになります。 また、継続して住むことが可能でも、建物・設備の故障や破損などで生活に支障があるときは、家賃の一部免除を求められる場合もありますので、それぞれに判断して預り金や家賃返還をする必要があります。
つぎに賃貸建物の修繕すべき箇所を特定して、予算とスケジュールを決めていきます。入居者の生活に欠かせない緊急的な修繕箇所は一日も早く復旧させるべき優先工事です。工事する人も資材も不足する混乱事態ですので、早めに計画して手を打つようにしましょう。
そして、加入している火災保険会社に連絡して折衝をします。そのために、被災状況を写真に収めたり、罹災(り
さい)証明書の申請も行動予定に入れておきましょう。
補助金や証明書などについて
被災時には国や自治体から補助金が支給される制度があります。
「災害弔慰金」は災害によって亡くなられた方の遺族に支給され、「災害障害見舞金」は災害によって精神又は身体に著しい障害を受けた方に支給されます。また「災害援護資金」は災害でケガをしたり、住まいや家財が被害を受けた方に、生活を立て直す資金を貸し付ける制度です。いずれも市町村が申請窓口となります。 罹災(りさい)証明書は、災害で“住居に生じた被害”を証明する各自治体が発行する公的な書類です。 この“住居”には持ち家と賃貸の区別はないので賃借人も申請できます。この証明書は、被災者が支援を受ける際に必要となりますが、主な支援とは、
- 応急修理制度:自宅修理の一部支援
- 災害援護資金貸付:負傷、家財損害、住宅の全半壊などで必要な資金を借りる
- 災害復興住宅融資:住宅の修理や再建費用を借りる
- 公費解体制度:建物を無償で解体・撤去
- 雑損控除:条件によって損害額が所得から控除
などになります。 最後に「賃貸型応急住宅」という制度について。これは災害によって居住困難となり自己では住宅確保が困難な被災者に対し、国や自治体が民間の賃貸住宅を借り上げて提供する一時的な住まいのことです。“みなし仮設住宅”とも呼ばれます。都道府県が、家賃、共益費、礼金、仲介手数料などを負担します。ここにオーナー様が賃貸住宅を提供するかはともかくとして、制度内容については知っておいて無駄ではありません。
いくら備えても万全にはなりませんが、地震災害のときに命と経営を守る術(すべ)については、可能な範囲の準備をしておきたいものです。
現状回復トラブルを避けるための予防策
賃貸経営において、退去時に起きる「原状回復」をめぐるトラブルは、消費生活センターへの相談の3~4割を占めるほど多く、特に紛争化しやすい事案です。こうした背景から、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」を策定し、裁判実務でもこのガイドラインが判断基準として用いられています。 したがって、原状回復トラブルを防ぐためには、ガイドラインの内容を正確に理解するとともに、貸主としてトラブルの予防策を尽くしておくことが重要です。
令和5年3月の改訂資料では、①契約内容の確認(特に特約)と物件状況の記録、②退去時の現地確認による認識共有が、予防のポイントとして示されました。この記事では、①の「ガイドラインと異なる特約」の注意点について解説します。
ガイドラインと異なる特約を定める場合の注意点
ガイドラインの参考資料で言及されている令和4年の管理会社を対象としたアンケート(以下「アンケート」)によれば、実務上は、ハウスクリーニング特約やエアコンクリーニング特約などが締結されることが多いようです。 このようなガイドラインの内容と異なる特約を設ける場合は、
①特約の必要性(合理的理由)
②条項の具体性(内容・金額の特定)
③賃借人の認識と同意(契約時には賃借人に対して特約の内容をしっかりと説明して明確に合意を得ること) の3要件を満たさなければ無効と判断されるリスクがあります。
実務上よく定められる特約
- ハウスクリーニング・エアコンクリーニング特約について
ハウスクリーニングやエアコンクリーニング特約は、実務上多く締結されています。クリーニング特約については、金額が妥当であり、賃借人に十分説明されている場合には、有効性が認められやすいです。国土交通省のガイドラインでは、原状回復工事施工目安単価を契約書に明記し、賃貸人・賃借人双方があらかじめ合意しておくことが推奨されていますので、ハウスクリーニングの目安単価は、実際のクリーニング業者の相場や、部屋の広さ・間取り等に応じて設定し、契約書や別表に具体的な金額(例:2万5000円(消費税別)など)を記載することが望ましいです。
2.喫煙によるクロス汚れについてクロスの全交換特約について
喫煙によるヤニ汚れや臭いは、一般的に通常損耗とは見なされず、賃借人の善管注意義務違反や用法違反に該当する可能性が高いです。そのため、特約を設けずとも、その修繕費用を賃借人に負担させること自体は可能です。
しかし、例えば「喫煙によるヤニでの変色や臭いがひどいときに、室内のクロス全面の交換費用を賃借人負担とする」といった特約を定める場合は、特に慎重な検討が必要です。 まず、なぜ汚れた部分だけでなく「全面」の交換が必要なのか、特約を有効とすべき客観的・合理的な理由が求められます。例えば、実際に「部分的な張替えでは色合いが異なり、賃貸物件室内の美観を著しく損なうため」といった理由があることが必要です。
次に、全面交換にかかる費用が、消費者契約法に定める「平均的な損害の額」を著しく超える場合、その特約は無
効となる可能性があります。特に、築年数が相当程度経過している場合や、クロス自体の残存価値が乏しい場合は、費用の過大性が問題となり得ます(この点は3で説明します)。 また、「喫煙した場合は室内のクロスを全面交換し、その費用を負担する」という義務を賃借人が負うことについて、契約時に極めて具体的に説明し、賃借人がその内容とリスクを明確に認識した上で合意していることが、有効性のための重要な要素となります。「重要事項説明書への明記」や「説明を受けた旨の署名・押印」等の証拠化が極めて重要です。
3.「経年劣化を考慮しない全額負担」特約の有効性
前述のとおり、喫煙によるクロスの汚損(タバコのヤニ汚れなど)は、通常の使用による損耗には含まれないと解釈されるのが一般的です。ただし、この場合でも、クロスの価値は経年により減少しているため、その減少分(経年劣化)を考慮せず喫煙による損傷を理由に交換費用全額を負担させる特約は、消費者契約法9条、10条に抵触し、無効と判断される可能性が極めて高いと考えられます。
したがって、このような特約を設けても無効となる可能性が高く、契約終了時に賃借人とトラブルになる可能性がありますので注意が必要です。
100年に1度!自動運転の普及で米国不動産に変化
アメリカではテクノロジー企業の進出により、不動産市場が急速に変化しています。アメリカで起きている変化をサンフランシスコの状況を中心に紹介します。
Airbnb(エアビーアンドビー)やUber(ウーバー)など日本でもなじみ深い有名なテック企業が本社を置く、ハ
イテク都市のサンフランシスコでは自動運転タクシーが一般化し、観光客にも人気です。他にも街中を電動キックボードなどが縦横無尽に走っており、こうした新しいモビリティによって自動車の所有率は毎年2%ずつ低下し、住
宅ビジネスや都市政策にも大きな影響を与えています。 例えば、市内では駐車場の廃止や再利用の議論が活発化し、家賃の安い郊外に引っ越す人も増加傾向にあるようです。現在は市内の一部エリアだけのサービスですが、今後も自動運転がさらに普及すれば、「駅近」や「バス便」と
いう従来の立地価値の概念にも変化が予想されます。
日本でも路上実験が進んでおり、今後の自動運転の普及で都市と郊外の距離感が変わる可能性があります。これまで通勤に不便だった地域が新たに注目される一方、車を所有しない世帯が増え、駐車場やガレージの設置要件が見直される可能性もあります。都市政策においても、移動データの活用や生活圏の再構築が求められそうです。
現地の専門家は、10年以内に自動運転が世界中に広がると予測されており、100年に1度の変化が間近に迫っている現実を感じます。
「契約」「投資」「内見」の領域でテクノロジーが進出
その他にも、住宅ビジネスの主要な接点である「契約」「投資」「内見」では、米国発のテクノロジーが次々に新し
い仕組みを生み出しています。その一つが、契約や入居審査をAIで効率化するFindigs(ファインディグス)です。
管理会社・オーナー双方にメリットがあり、従来に比べ、時間も手間も大幅に削減できます。日本でも、こうしたAI契約の波が押し寄せるのは時間の問題でしょう。
- STEP 1:入居希望者が申請
- STEP 2:Findigsが申請情報をAIでスコアリング(審査)
- STEP 3:自動で審査結果を通知(合否)
- STEP 4:オンラインで契約書を作成・署名
- STEP 5:スムーズに入居へ
投資の領域では、Arrived Homes(アライヴド・ホームズ)が新たな潮流を生んでいます。住宅を小口化し、個人投資家が少額から不動産オーナーになれる仕組みを提供しています。アメリカでは数百ドルから不動産投資が始められるので、若い世代の投資家の参加が増えています。
投資から管理までがオンラインで完結する点も特徴です。日本でもNISAやクラファンによる「少額不動産投資」が拡大しており、今後は新しい不動産投資の形として参考になりそうです。
- STEP 1: Arrived Homesが物件を用意
- STEP 2:投資家が少額(例:100ドル~)で出資
- STEP 3:不動産が小口化され、複数人で所有
- STEP 4:家賃収益などを按分して受け取る
- STEP 5:投資家はオンラインで状況を管理
内見の現場でも、Matterport(マターポート)の3Dスキャン技術により、現地に行かずとも高精度なVR内見が可能になっています。「特に遠方からの契約や高額物件での決断を後押しする強力なツールになる」と現地のエージェントは語っています。コロナ禍で注目されたオンライン内見は日本にも広がりつつありますが、まだ業界全体に浸透しているとは言い難い状況です。 スマホやPCで複数物件を比較検討できるため、今後さらに活用が広がりそうです。
- STEP 1:現地の物件を3Dスキャン(Matterport使用)
- STEP 2: バーチャルツアーをWeb上で公開
- STEP 3:ユーザーがスマホやPCで内見体験
- STEP 4:複数物件を比較し、遠方からでも検討・決断
アメリカの事例から分かるのは、不動産ビジネスの主要な接点がテクノロジーによって再定義されつつあるということです。立地の基準が自動運転で変わり、契約はAIによって迅速になり、投資は小口化で門戸が広がり、内見は3D化で時間や場所の制約から解放されます。これらの変化は、単なる効率化を超えて、住宅に関するトレンドや選択肢そのものにも影響を与えつつあります。 日本では、高齢化や都市集中、空き家問題といった独自の課題がありますが、テクノロジーをうまく取り入れれば解決の糸口になるかもしれません。今後、どの企業のサービスが日本市場で定着し、どのようなプレーヤーが新しい価値を創造するのでしょうか。できれば、日本発の企業やサービスがもっと現れるのを期待しつつ、動向を注視していきたいと思います。
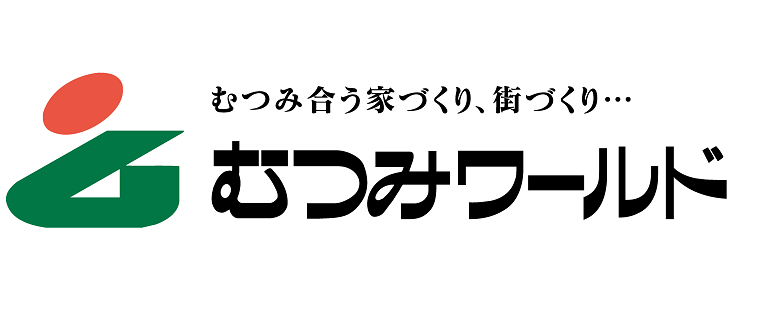
- Tags
- 人気のタグ
- Rerated
- 関連記事