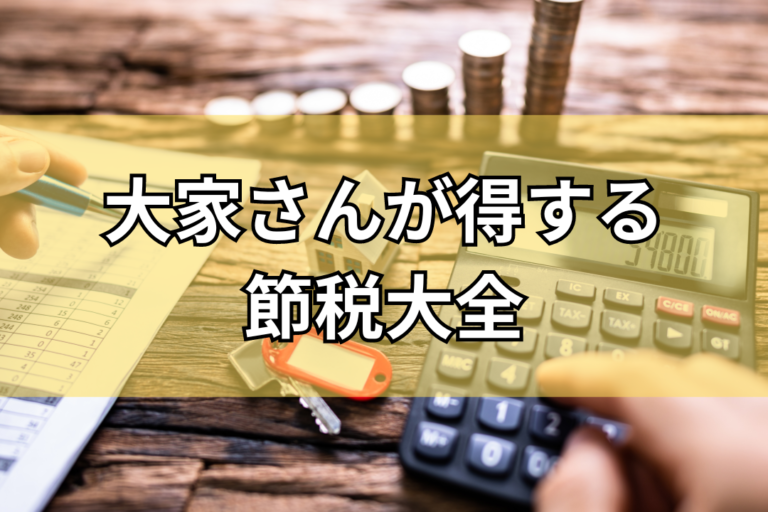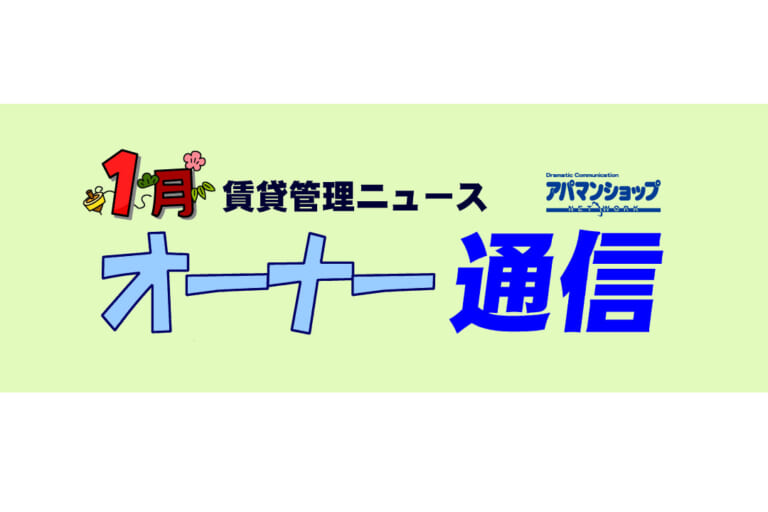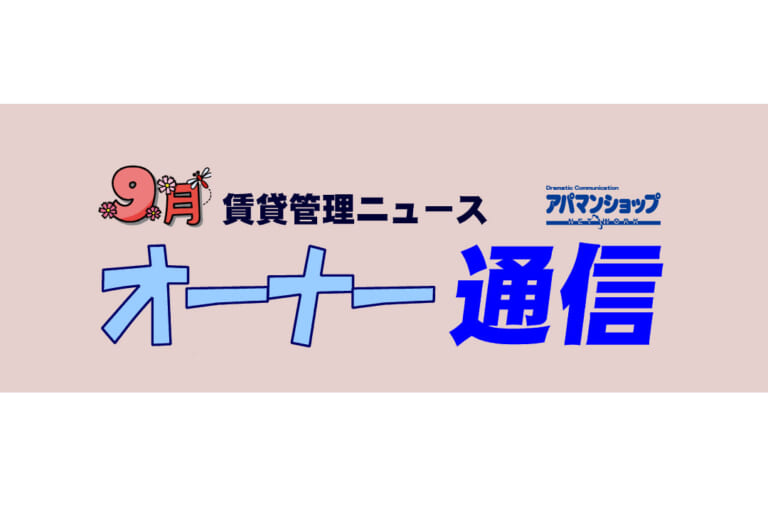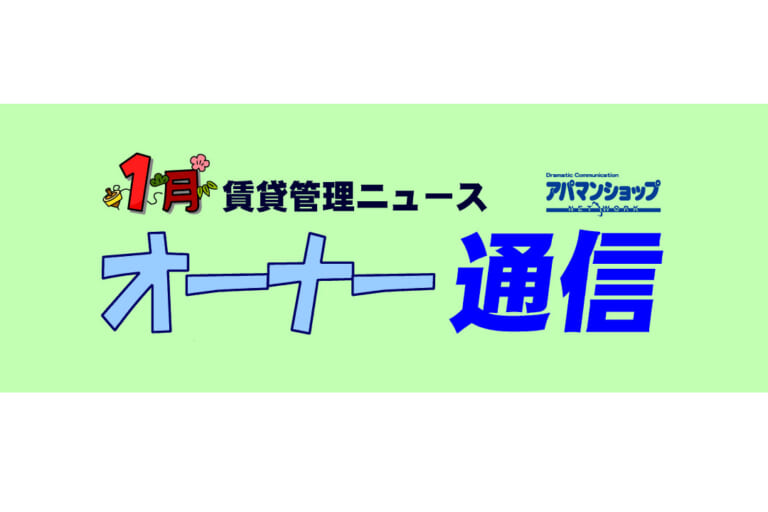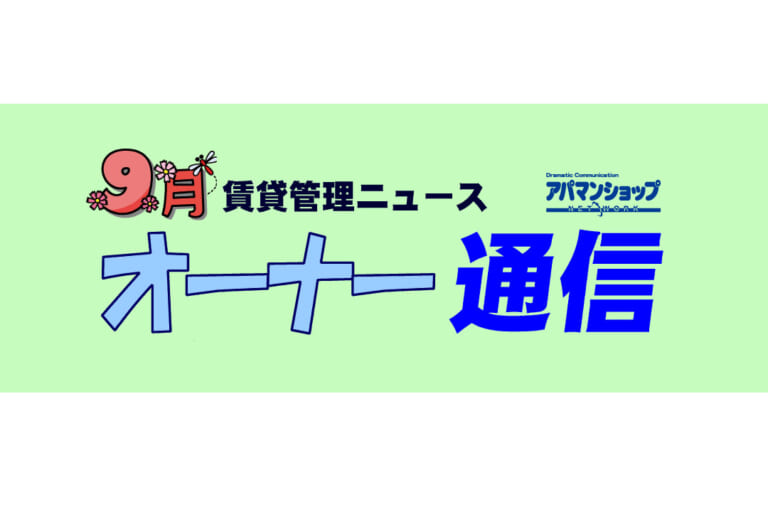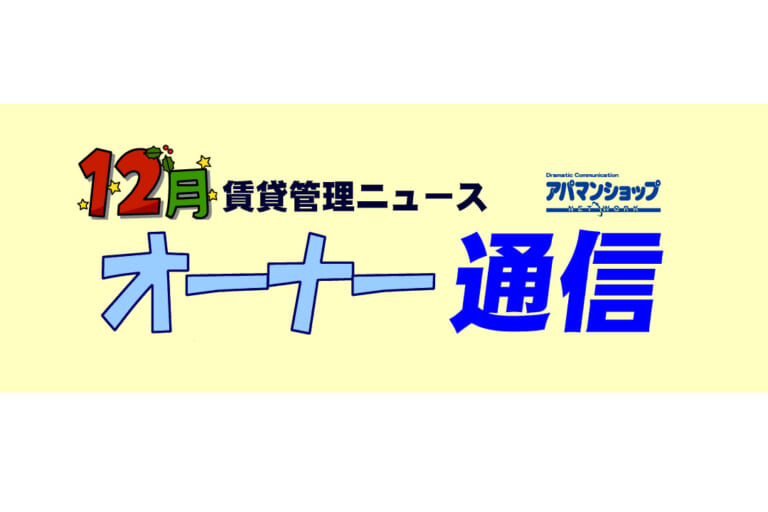- 2025.11.06
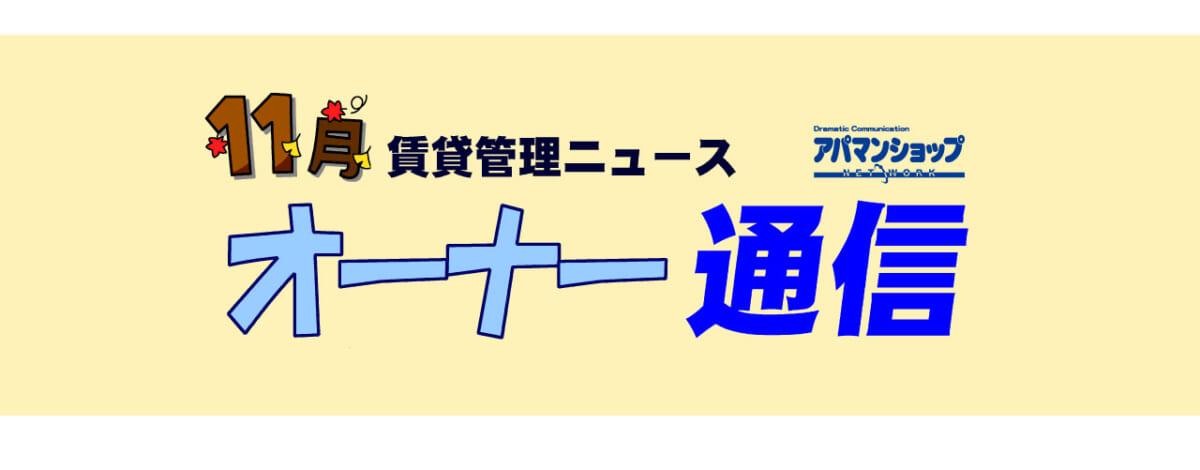
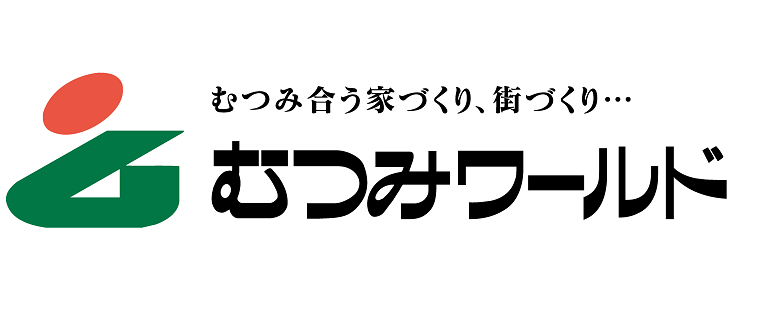
インボイス時代の“勝ち筋” 法人化は数字ではなく設計で決める
多くの物件を運営されるオーナー様にとって、「法人化」は事業の成長段階における重要な経営判断の一つです。ご存知の通り、個人の所得税は累進で、所得が増えるほど急勾配に上がります。一方で法人側の実効税率は個人ほど急勾配ではないものの、利益規模に応じた段階性があります。判断は“単発の節税”ではなく、3年キャッシュフロー(CF)で資金が増える設計かどうか、です。
かつて、その損益分岐点の目安が「個人の課税所得900万円」と一般的に言われてきました。 この考え方は基本ですが、2023年10月に開始されたインボイス制度をはじめとする近年の変化により、法人化を判断する視点はより多角的になっています。最新の動向を踏まえ、あらためて法人化を検討する上で重要となるポイントを解説いたします。
たとえば、住居中心に1階テナントと月極駐車場を持つオーナーKさんの場合。外壁と屋上の改修に2,000万円(税抜)を予定。税理士から「法人化も視野」と言われたが踏ん切りがつかない。ここで①税額②会社負担を含む社会保険料③改修の消費税処理を重ねて検討。まず入口で迷わないために、税金だけの超シンプル比較で“方向性”を掴みます。
【ざっくり比較】税金だけで見たらどっちがお得? (個人vs法人)
前提:年間の儲け(課税所得)が 1,000万円 の場合
- A 個人事業主のまま
儲けの分け方:すべて個人の所得 課税所得:1,000万円
税金の内訳:個人の税金(概算)所得税:176.4万円(33%-速算控除)住民税:100万円(約10%)
税金の合計:約276万円
- B 法人化した場合 儲けの分け方:役員報酬と会社の利益に分ける 役員報酬:600万円 会社の利益:400万円 税金の内訳:会社の税金(概算)法人税など:120万円(30%仮置き) +役員個人の税金(概算)(給与所得控除・社保控除・基礎控除後)所得税:約20万円 住民税:約30万円 税金の合計:約170万円
年間の差額A-B:法人が 約106万円 お得!
すなわち、税金だけで見ると法人が約106万4,000円有利※1という“方向性”が見えます。
ここからが実務です。Kさんは改修年の消費税(仕入控除の按分)や会社負担の社会保険まで含めて3年CFを作成。
事業用・駐車場の“課税売上”があるぶん、改修に含まれる消費税の回収余地が生まれる一方、役員報酬に応じた会社負担の社会保険が新コストとして発生。この2つを投資の年度配分と合わせ、方式選択(個別対応/一括比例※2、役員報酬の置き方を微調整した結果、「改修を起点に資金を回収→再投資」の道筋が描け、Kさんは法人化を選びました。 一方、住居のみで運営している場合は、居住用賃料が原則非課税のため、インボイスや課税事業者選択の効果は限定的。ここでの判断軸は消費税ではなく、「所得税+会社負担社保」を合わせた総コストに移ります。
結局のところ、同じ“法人化”でも勝ち筋はポートフォリオで変わるのです。本質はシンプルです。
1.どんな収益で資金が入るか(住居中心か、事業用や駐車場をどれだけ含むか) 2.いつ、いくら投資するか(改修・取得の時期と規模) 3.役員報酬と社会保険をどう設計するか(期中で動かしにくい前提を踏まえる)
この3点を同一の時間軸(3年CF)で重ね、“税+社保+投資”の合算でプラスが出る設計を選ぶ。ここに、インボイス以後の法人化判断のコアがあります。 さらに、承継まで視野に入れるなら、資産そのものではなく株式で移す選択肢が広がります。議決権や分配の設計、後継者の関与ステップを柔軟に描けるのが法人の強み。短期の節税だけでなく、10年の資本政策を一本化できる点も見逃せません。最後に、今すぐやることを3つだけ。
1.直近3年の賃料内訳と、向こう3年の投資予定を一覧化する。 2.役員報酬案+会社負担社保を載せた3年CFを作る(期中変更不可の原則を前提)。 3.税理士と、消費税の方式とスケジュール(原則課税/簡易、按分の考え方)を決める。
結論は「法人化すべき/すべきでない」ではありません。
“資金が増える設計を選ぶか”です。本稿は2025年9月時点の制度を前提とした一般解説です。最終判断は、顧問税理士・社労士と3年CFでの個別試算を行ったうえで決定してください。
※1.この比較は税金のみです。法人化では会社負担の社会保険(例:報酬600万円で年約90万円)が別途発生し条件次第で逆転します。住民税は均等割等を無視した概算で、実額は控除・料率・地域で変動します。「個人:課税所得1,000万円」(控除後)に対し、法人側は「会社400万円課税所得+役員報酬600万円(控除適用後の課税所得≒300万円)」という配分モデルでの方向性比較です。
※2.方式選択:支払った消費税を、課税売上と非課税売上にどう振り分
けるかの計算方法(個別対応方式/一括比例配分方式)
滞納2 ヶ月でも契約解除は可能?
弁護士が裁判例で解説する家賃トラブルの判断基準
賃料を支払わずに音信不通になる、あるいは少額入金を繰り返すといった入居者の対応にお悩みではありませんか。今回は、そうした賃料支払いに問題を起こす入居者に対する「賃料不払いによる契約解除」の法的な考え方を、実際の裁判例を通じて解説します。
賃料不払いによる契約解除の可否とその基準
賃貸オーナー様から弁護士に寄せられる相談で多いのは、原状回復と賃料不払いの紛争です。賃料の支払い義務は、賃貸借契約における賃借人の最も重要な義務です。したがって、この義務を誠実に履行しない賃借人に対し、
賃貸人が契約解除を求めるのは当然の流れです。しかし、賃料の不払いが一度でもあれば、必ず契約を解除できるわけではありません。ここで問題となるのが「信頼関係破壊の法理」です。これは、賃借人の契約違反が、当事者間の信頼関係を破壊するほど重大なものでなければ、契約解除は認められないという考え方です。つまり、形式的な契約違反だけでなく、その程度や背景が問われます。
では、どの程度の賃料不払いであれば契約解除が可能なのでしょうか。
裁判実務では、原則として「賃料の不払いが合計3ヶ月分に達した時点」で信頼関係が破壊され、解除が可能になるという基準が概ね確立されています。ただし、この「3ヶ月分」という基準はあくまで目安です。その他の事情を考慮し、滞納が3ヶ月未満でも解除が認められたり、逆に3ヶ月に達していても解除が認められなかったりする裁判例もあります。以下では、対照的な2つの事例を紹介します。
2ヶ月分の賃料不払いで解除が認められた事例
東京地裁平成29年5月25日判決は、2ヶ月分の賃料不払いで解除を認めた裁判例です。この事案の賃借人は「管理費が高額だ」と一方的に主張し、5ヶ月にわたって毎月1万円を減額して支払い続けました。保証会社が不足分を代位弁済していましたが、その後2ヶ月は賃料を全く支払わなかったため、賃貸人が解除を通知しました。このような一方的な減額行為は、オーナー様が遭遇しがちな「逆ギレ」に近い態度と見なされることもあります。
実際、裁判所は2ヶ月分の不払いに加え、賃借人が5ヶ月間も独断で減額を続けたことや、管理費減額等の不当な
要求を執拗に行った等の背信的態様を総合的に評価しました。その結果、信頼関係の破壊を肯定し、契約解除と建物の明渡しを認めたのです。このように、滞納月数が形式上2ヶ月分であっても、少額入金の継続や不当な要求といった他の背信的な事情が重なれば、信頼関係の破壊が認められる可能性は高まります。
3ヶ月分の賃料不払いでも解除が認められなかった事例
東京地裁平成25年4月16日判決は、3ヶ月分の賃料不払いでも直ちには契約解除を認めなかった裁判例です。
この事案では、賃借人が3ヶ月分の賃料を滞納したため、賃貸人は支払期限(6月6日)を定めて催告しました。期限内に支払いがなかったため翌7日に解除通知を発したところ、賃借人はさらにその翌日の8日に、滞納していた3ヶ月分を一括で弁済しました。
なお、この事案の特殊事情として、滞納が起きる前から賃借人が賃料減額の調停を申し立てており、話し合いが継
続している最中での出来事でした。このケースで裁判所は、6月7日の解除通知について、調停係属中であったことや、催告期限のわずか2日後に滞納していた3ヶ月分が一括で支払われた事情を重視しました。
そして、この時点では信頼関係の破壊には至っていないとして、解除を無効と判断しました。他方で、この賃借人はその後も不払いを続けた(この間、わずか6万円の少額入金があったのみ)ため、賃貸人が11月6日に再度行った解除の意思表示は、長期の不払いにより信頼関係が破壊されたとして有効とされ、最終的に明渡しが命じられています。以上のとおり、「3ヶ月分の滞納」は絶対的な基準ではなく、不払いの理由や解除通知に至る経緯、その後の対応などを総合的に考慮して、解除の可否が判断されることがわかります。
「賃料3ヶ月分の不払いによる解除」は裁判実務で確立された基準ですが、その根底には常に「信頼関係が破壊さ
れたか」という判断軸があります。したがって、賃料不払いで紛争中の賃借人がいる場合、契約解除を確実にするためには、交渉の経過など賃借人の問題行動を証拠化しておくことが極めて重要です。
例えば、電話内容の録音、少額入金や支払い遅延の正確な記録、不当な要求が書かれたメールやLINE などの保存です。これらの記録は、単なる滞納月数だけでなく、賃借人の悪質性や背信性を客観的に立証し、より確実な契約
解除へと繋げるための鍵となります。
【来年度予算案】国の7兆円は賃貸経営にどう流れる?
オーナーが知るべき4つの未来図
国土交通省が来年度に向けてまとめた概算要求は、一般会計で7兆812億円と今年度に比べて19%の大幅増となりました。今年1月に埼玉県八潮市で発生した道路陥没などを受け、全国のインフラ老朽化対策に1兆円規模を投じるためです。さらに、土砂災害や地震、津波に備えた防災・減災対策にも1兆円余を盛り込みました。
インフラ維持が最優先される一方、住宅分野でも賃貸経営に直結する政策の方向性が見えてきます。空き家対策、高齢者や子育て世帯への支援、改修工事の補助、さらには不動産市場のDX化など。来年度予算は、オーナーにとって「これからの賃貸経営の大きな流れ」を先取りする内容といえそうです。
1.空き家・相続問題が対策を迫る
日本の空き家はこの20年間で急増し、2003年の約212万戸から2023年には約385万戸へと1.8倍に膨らみました。今後は相続をきっかけに、さらに大量の空き家が発生すると予測されています。国はこの流れに対応し、除却や再生に対する補助を強化、自治体や専門法人による管理・活用を後押しする方針です。
賃貸住宅も、将来的に空き家となるリスクを抱えています。オーナーには、早い段階から出口戦略を描くことが欠かせなくなりそうです。物件を維持・再生して次世代に引き継ぐのか、それとも市場で売却して資金を回収するのか。国の支援制度も意識しつつ、自分の物件を「空き家予備軍」として見据えておくことが求められる時代に入っています。
2.高齢者・子育て世帯への対応が不可欠に
単身高齢者の世帯は年々増加し、2030年には887万世帯に達すると見込まれ、孤独死リスクが社会問題化しています。国交省は居住支援法人による見守り等を制度化し、オーナーが高齢者に部屋を貸しやすい仕組みづくりへ予算要求を行いました。賃貸経営の現場では「貸しにくい層」への対応がますます重要になります。 高齢者をどう取り込むか。「国交省概算要求を読むと、空室対策であると同時に、地域社会におけるオーナーの役割を拡大する試みに繋がる可能性も見えてきます」(経済紙・記者)
3.改修投資を後押しする補助金
住宅の省エネ化やバリアフリー改修を対象とする支援制度も拡充されます。2025年4月には省エネ基準の義務化が開始。さらに2030年には、新築全体の平均でZEHやZEB水準の性能を目指す政策目標が掲げられ、これに合わせて既存建物の改修を後押しする補助金が組まれました。
古い賃貸物件を抱えるオーナーには、修繕や改修に先手を打つかどうかが経営を左右します。放置すれば家賃下落や入居率低下につながりますが、補助金活用で早めに設備を更新すれば、入居者の満足度向上と資産価値の維持につながるかもしれません。
特に給湯器や空調など更新サイクルの短い設備は、円安や資材高騰の影響で負担がかさみます。国の支援を活か
し、省エネ機器や断熱改修を進めれば、長期的なランニングコスト削減にもつながるでしょう。来年度に向けて今から準備しておくべき話題になりそうです。
4.DXで物件情報の広がりに変化が
不動産市場の透明化を目指し、国は「不動産ID」の導入を進めています。住所や建物を一意に特定できるようになる仕組みで、令和9年度から試験運用が始まる予定です。加えて、不動産情報ライブラリの整備が進められており、物件ごとに価格、災害リスク、都市計画などの情報が統合的に表示できるようになりました。
不動産ID導入:・住所・建物特定 不動産情報ライブラリ:・価格・災害リスク・都市計画 など オーナーへの影響:隠す経営→難しい 見せる経営→チャンス
「不動産IDや情報ライブラリは、『情報を隠す時代』の終わりを意味します。これはオーナーにとって不利にはたらくと同時に、チャンスにもなります。耐震補強や省エネ設備をアピールすれば、むしろ差別化要因になる。つまり隠すより見せる経営が問われるようになる」(経済紙・記者)たとえば、耐震補強や省エネ改修の実施状況を積極的
に開示し、安心や快適さをアピールすることが重要になるでしょう。 その他の設備投資もより積極的にプラスの評価に繋がるかもしれません。DXは単なるデジタル化ではなく、オーナーの姿勢を大きく変える契機となりそうです。
来年度予算の概算要求はたたき台ですが、今後具体的な制度設計が固まっていきます。オーナーや事業者にとっての実利がどの程度になるのかは、これからが本番です。引き続き注視しながら、この欄でも動きを追って紹介していきたいと思います。
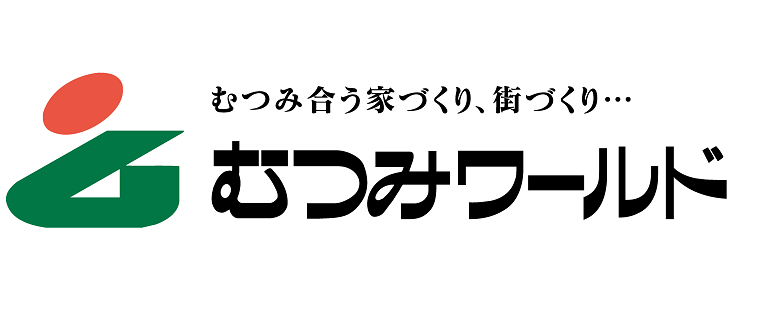
- 賃貸経営
- 2025年11月の賃貸経営管理ニュース
- Tags
- 人気のタグ
- Rerated
- 関連記事